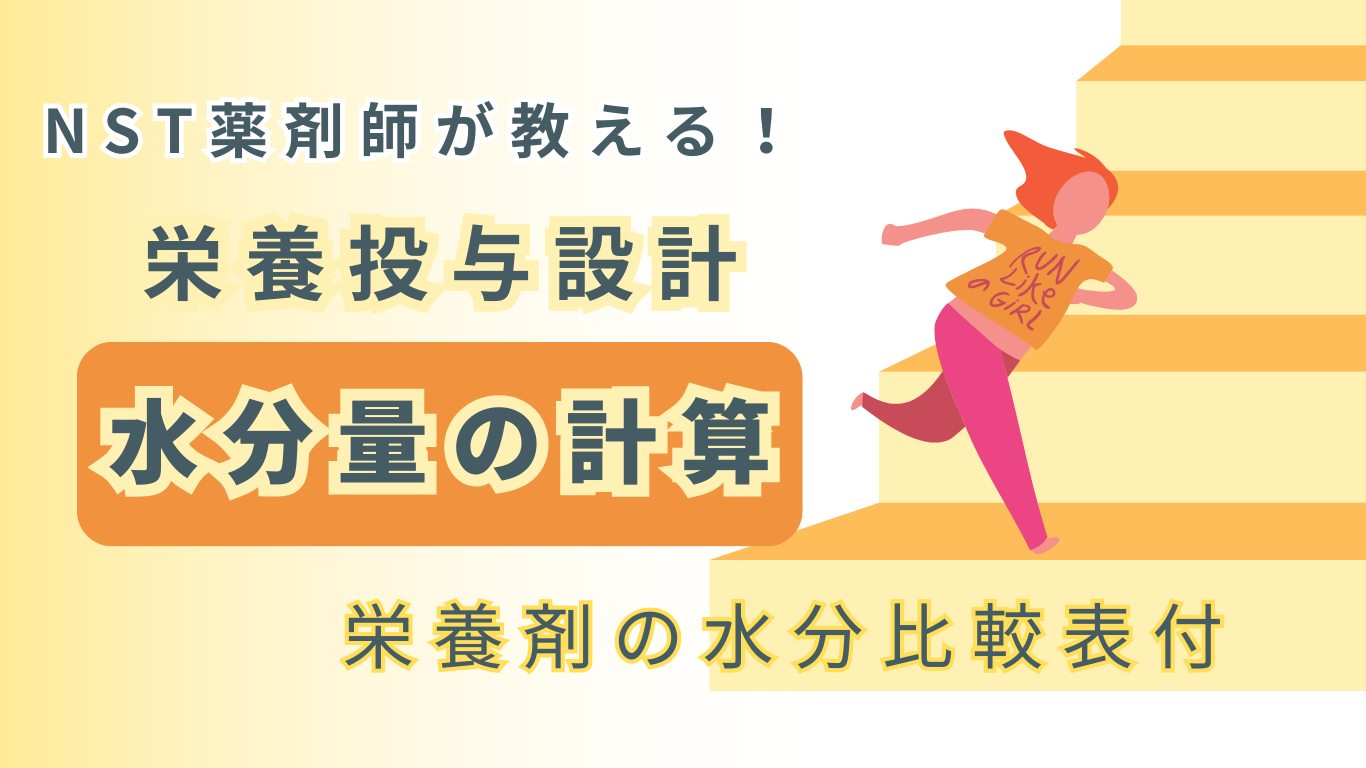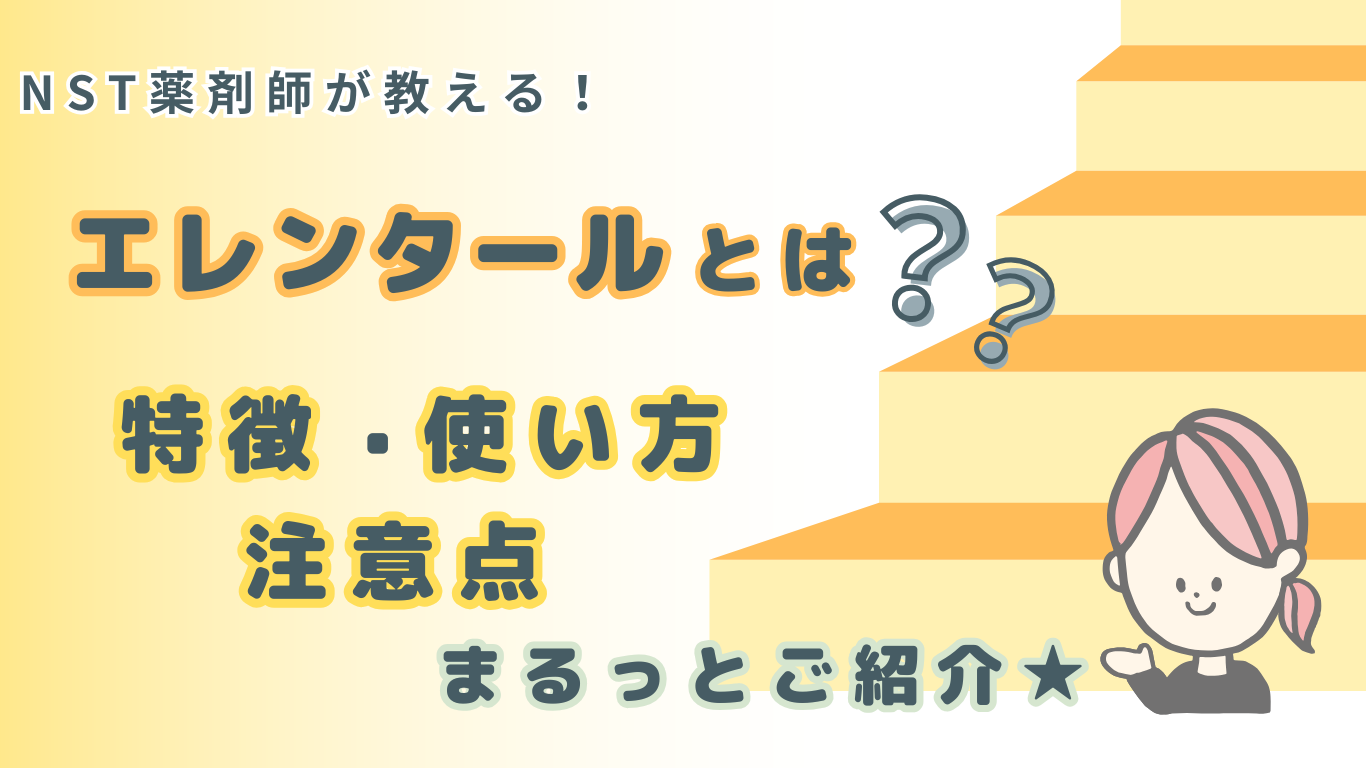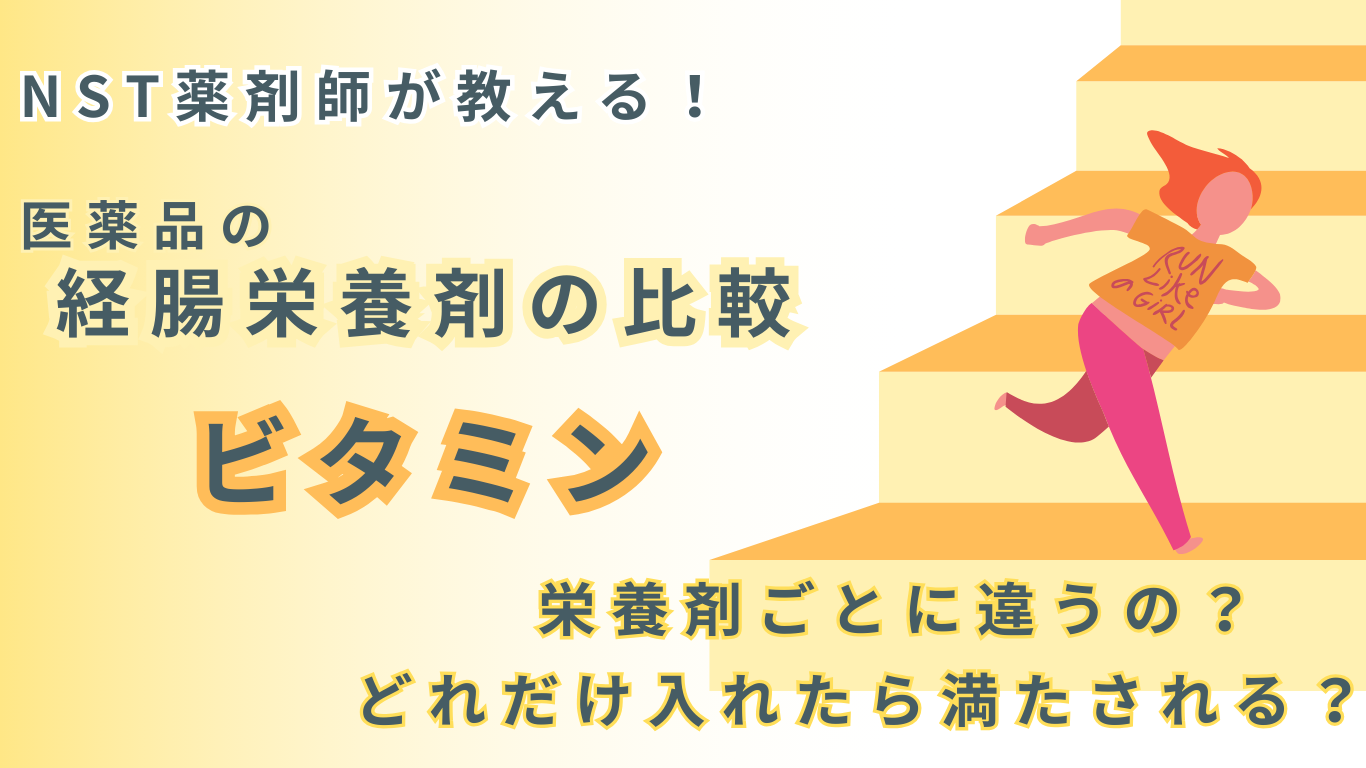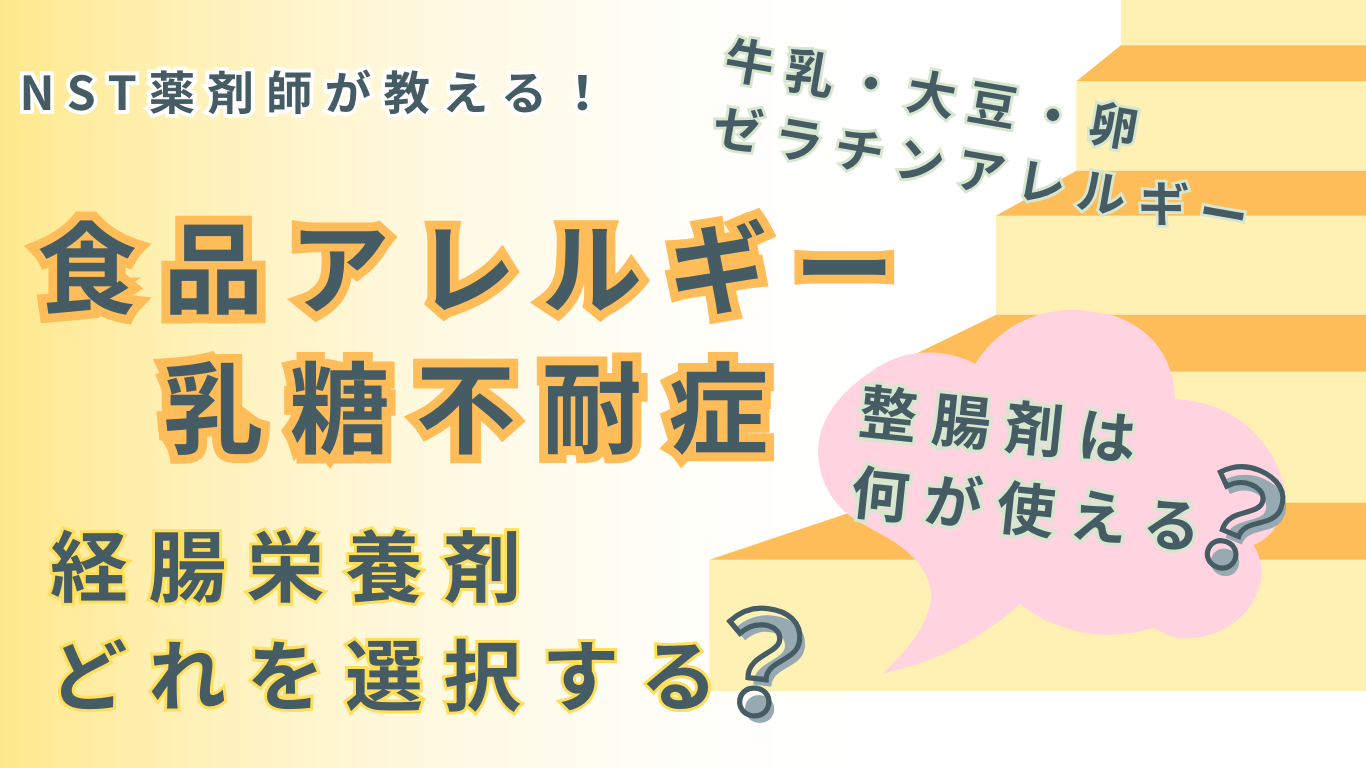経腸栄養剤の浸透圧の違い、選び方 NST薬剤師が教える覚えておくべきポイント
NST薬剤師のkeikoです。今回は経腸栄養剤の浸透圧の違いについての記事にしました。
早速ですが、経腸栄養剤で”浸透圧”について覚えておくポイントは以下の通りです。
ここで終わっても良いですが、これらの理由や臨床に生かすために必要な知識についてもまとめました。
これらの疑問を具体的な経腸栄養剤も交えてご紹介します。
自分で扱ったことのある製品と知識を結びつけて覚えていただけたら、きっと臨床で生かすことができますよ。
そもそも浸透圧とは?
ある箱に水だけが通ることができる仕切り(半透膜)を入れて、各々に濃度の異なる液体を入れます。そうすると、水は濃度の低い方から濃度の高い方へ、濃度が同じになるように引っ張られます。
浸透圧は、この濃度差で水を引っ張る力のことをいいます。
この濃度は1L中に溶けている粒子の数(mOsm)で示されています。
そのため、単位は”mOsm/L”です。
経腸栄養剤の浸透圧の違いとその理由1
【理由】
タンパク質の組成(窒素源)による違いが理由です。
主な窒素源は成分栄養はアミノ酸、消化態栄養はジペプチドやトリペプチド、半消化態栄養はタンパク質です。
アミノ酸x2 ≒ ジペプチド
アミノ酸x3 ≒ トリペプチド
アミノ酸x沢山 ≒ タンパク質
アミノ酸、ペプチド、タンパク質は上記のように、アミノ酸が連なってできたものがペプチド、タンパク質といった関係になります。
アミノ酸はサイズは小さいけど、タンパク質と同じだけのアミノ酸を入れようとすると(粒子の)数は多くなります。逆に、タンパク質はサイズは大きいけど、合体しているため(粒子の)数は少なくなります。
”1.そもそも浸透圧とは” に記載したように、
粒子の数が多い=浸透圧が高い
つまり、タンパク質の組成(窒素源)が
・アミノ酸の成分栄養は、粒子の数が多い=浸透圧が高い
・タンパク質の半消化態栄養は、粒子の数が少ない=浸透圧が低い
このようになります。消化態栄養はその間だという認識でOKです。
以下、分類別で経腸栄養剤の浸透圧の比較です。
成分栄養が高く、半消化態栄養の方が低いですね。
| 経腸栄養剤 | 浸透圧 (mOsm/L) | ||
| 成分栄養 | エレンタール | 755 | 高 |
| 消化態栄養 | ツインライン | 470~510 | ↑ |
| 半消化態栄養 | エンシュア・リキッド | 330 | 低 |
| ラコールNF(液体) | 330~360 | ||
経腸栄養剤の浸透圧の違いとその理由2
【理由】
濃度が濃いということは、同じ液体中に溶けている粒子の数が多くなります。
つまり、粒子の数が多い=浸透圧が高い です。
以下、半消化態栄養剤の濃度と浸透圧の比較です。
濃度が高いほど、浸透圧も高くなっていますね。
| 経腸栄養剤 | 濃度 | 浸透圧 (mOsm/L) | ||
| 半消化態栄養 | エンシュア・リキッド | 1 kcal/mL | 330 | 低 |
| ラコールNF(液体) | 1 kcal/mL | 330~360 | ||
| エンシュア・H | 1.5 kcal/mL | 540 | ↓ | |
| イノラス | 1.6 kcal/mL | 670 | 高 | |
浸透圧と下痢
浸透圧は濃度の低い方から濃い方へ水を引っ張る力と前述しました。
血漿浸透圧は285±5 mOsm/L です。
これより高い浸透圧のものを入れると、血漿から腸へ水が引っ張られます。
腸の中に水が増え、増えすぎてしまうと下痢になってしまいます。
そのため、浸透圧が高い経腸栄養剤を投与すると下痢になりやすいというわけです。
基本的に、経腸栄養剤はどれも血漿浸透圧より高いため、どれも下痢になる可能性はあります。
どのくらいリスクがあるのかを認識したうえで、使い分けていただけると良いと思います。
経腸栄養剤は薄めても良いか?
浸透圧に影響する因子として、タンパク質の組成と濃度ということがわかった!
経腸栄養剤の組成を変えることは自分でできないけど、水で薄めることはできる!
じゃあ、経腸栄養剤は薄めても良いの?ということですが、
栄養剤は絶妙なバランスで作られています。ここに無菌操作もせずに、無菌でもない水を混ぜてしまうと細菌汚染のリスクが高まってしまうため、おすすめはされていません。
エレンタールに関しては、元々粉末の製品のため水で溶解する“量”を変更すれば良いので、細菌汚染リスクと関係ないのでは?
と思われるかもしれませんが、実は浸透圧が低いと細菌の水分活性が高いため汚染リスクは高くなると言われています。(料理でいう、塩漬けや砂糖漬けは浸透圧を上げることで保存期間を長くすることができています)
じゃあ浸透圧が低いものはそもそも細菌汚染リスクが高いのか・・・
と理論的にはそうですが、くり返しますが栄養剤はとても絶妙なバランスで作られており、経口であれば8時間までは細菌汚染なく投与ができると言われています。
ちなみに希釈について、各添付文書には以下の記載があります。
経腸栄養剤を利用している方の下痢の原因は様々です。
投与速度減速や病態から下痢を起こしているケースなど他で対応できることをまず考える必要があります。
どうしても希釈する必要があるという場合には参考にしてみてください。
高濃度の製品は原則、希釈せず低濃度の製品に変更しましょう。
| 希釈可否 | 希釈に関する記載事項 | |
| エレンタール | ○ | 初期量は、 1 日量の約1/8(60~80g)を所定濃度の約1/2(0.5kcal/mL)で投与開始し、患者の状態により、徐々に濃度及び投与量を増加 |
| ツインライン | ○ | 年齢、体重、症状により投与濃度を適宜増減する 小児では、約0.4kcal/mLの濃度より投与を開始し、臨床症状を注意深く観察しながら、徐々に濃度を上昇させること。なお、標準濃度は0.7~0.8kcal/mLとする |
| エンシュア・リキッド | ○ | 初期量は標準量の1/3~1/2量とし、水で約倍量に希釈 (0.5kcal/mL)して投与する。以後は患者の状態により徐々に濃度及び量を増し標準量とする。 |
| エンシュア・H | × | 低濃度(1kcal/mL以下)の他の経腸栄養剤を投与し、 下痢等の副作用が発現しないことを確認すること。 |
| ラコールNF(液体) | ○ | 投与開始時は、通常1日当たり400mL(400kcal) を水で希釈(0.5kcal/mL程度)して、低速度(約 100mL/時間以下)で投与し、臨床症状に注意しながら 増量して3~7日で標準量に達するようにする。 |
| イノラス | ー | ー |
浸透圧の違いで、経腸栄養剤を選べば良いか
消化管機能低下、障害があると?
浸透圧が低くても栄養を吸収することができないので、下痢を生じてしまいます。
そういった患者さんに浸透圧を下げるために、半消化態栄養の浸透圧を低いものを選んでも効果は△です。
→そもそも吸収できていないので、タンパク質の組成(窒素源)がアミノ酸で、消化不要な成分栄養が望ましいです。
消化吸収低下がないor軽度では?
消化吸収がある程度できるのであれば、
タンパク質組成の半消化態栄養は最初から投与できます。
その中で浸透圧性の下痢のリスクに応じて、経腸栄養剤の浸透圧の違いから選ぶことも選択肢の一つです。
腸を使っていない期間が長く消化吸収機能が低下している可能性があれば、浸透圧低いものから選びます。
食事が問題なくとれているけど補食のために使用する等のときのように、消化吸収機能が問題ないようであれば浸透圧が高い高濃度製品から開始もできます。高濃度製品でゆっくり摂取しても下痢が生じてしまう時には、浸透圧を下げるために基準の1kcal/mLの製品に変更を考慮します。
※注意点:浸透圧が異なると水分量も異なります。水分摂取量や水分制限についても忘れないようにご注意ください。
※経腸栄養剤で下痢が生じる場合には、半固形製剤の利用もご考慮ください。医薬品の半固形製剤は胃瘻からの投与を目的としているため、経口投与は適応外となり使用できませんが、市販品であれば使用できます。
以上、経腸栄養剤の浸透圧について覚えておくと役立つであろうことをまとめました。
皆様のお役に立つことができれば嬉しいです。