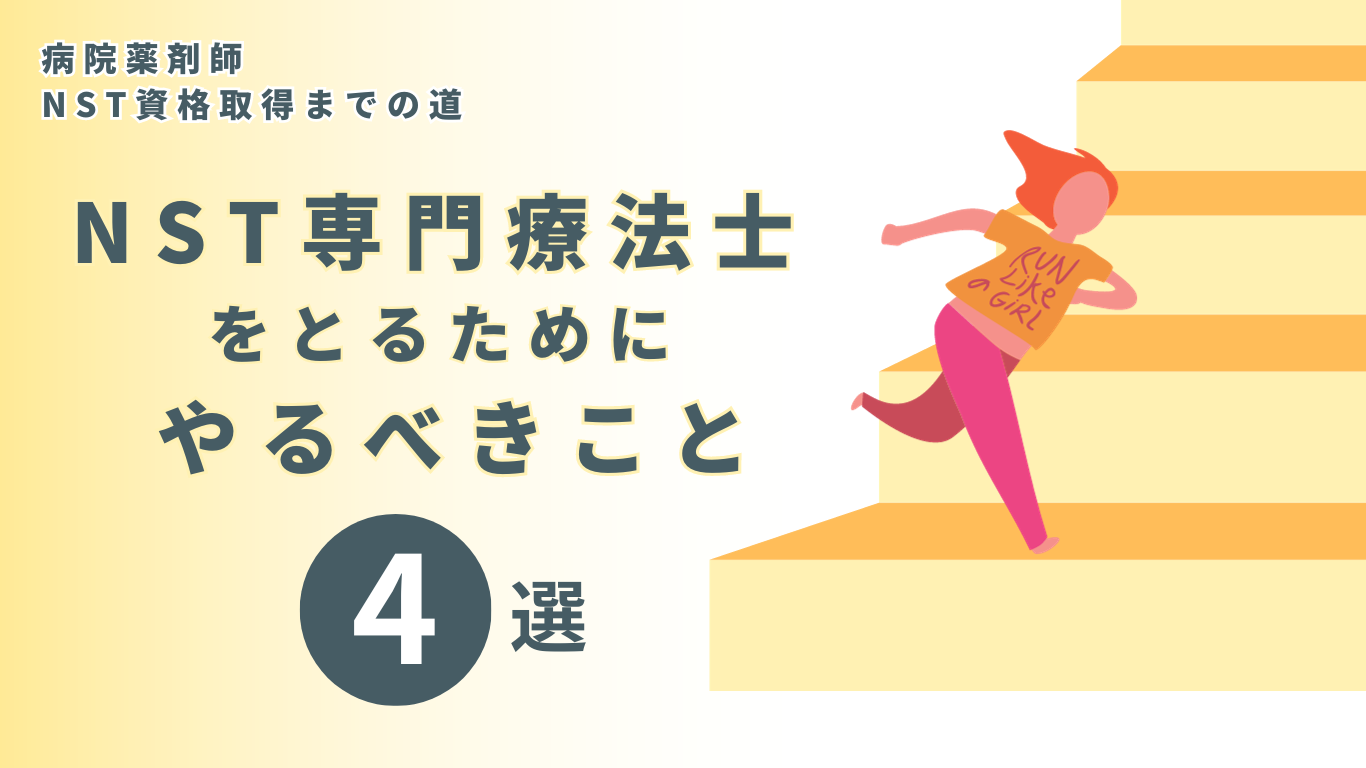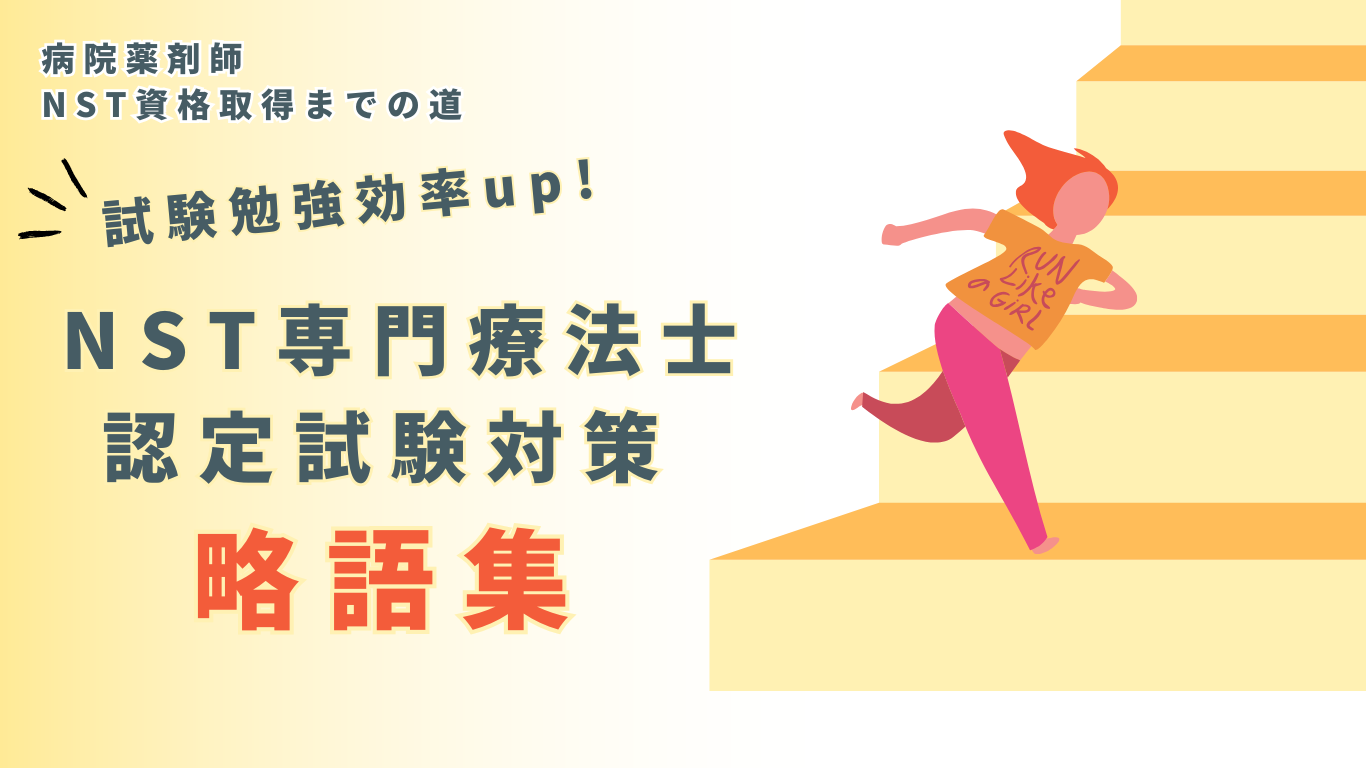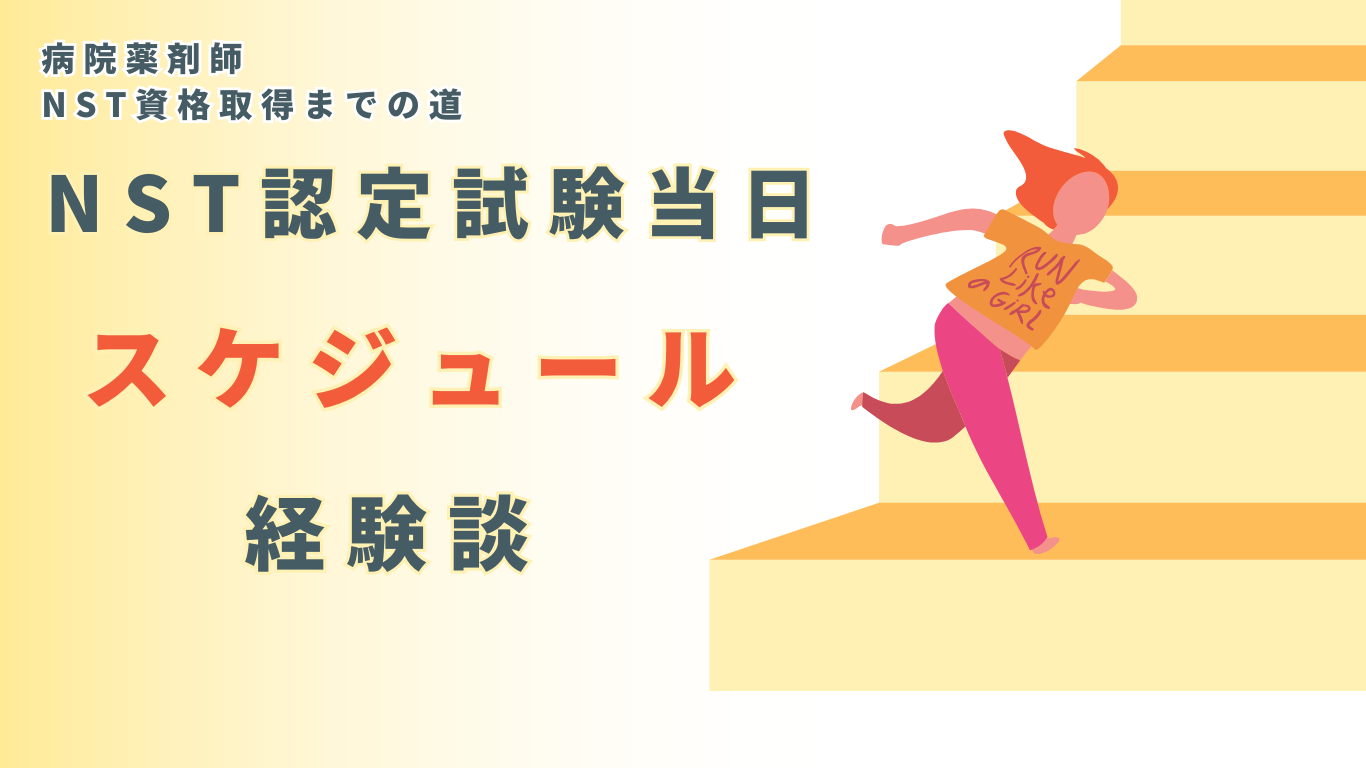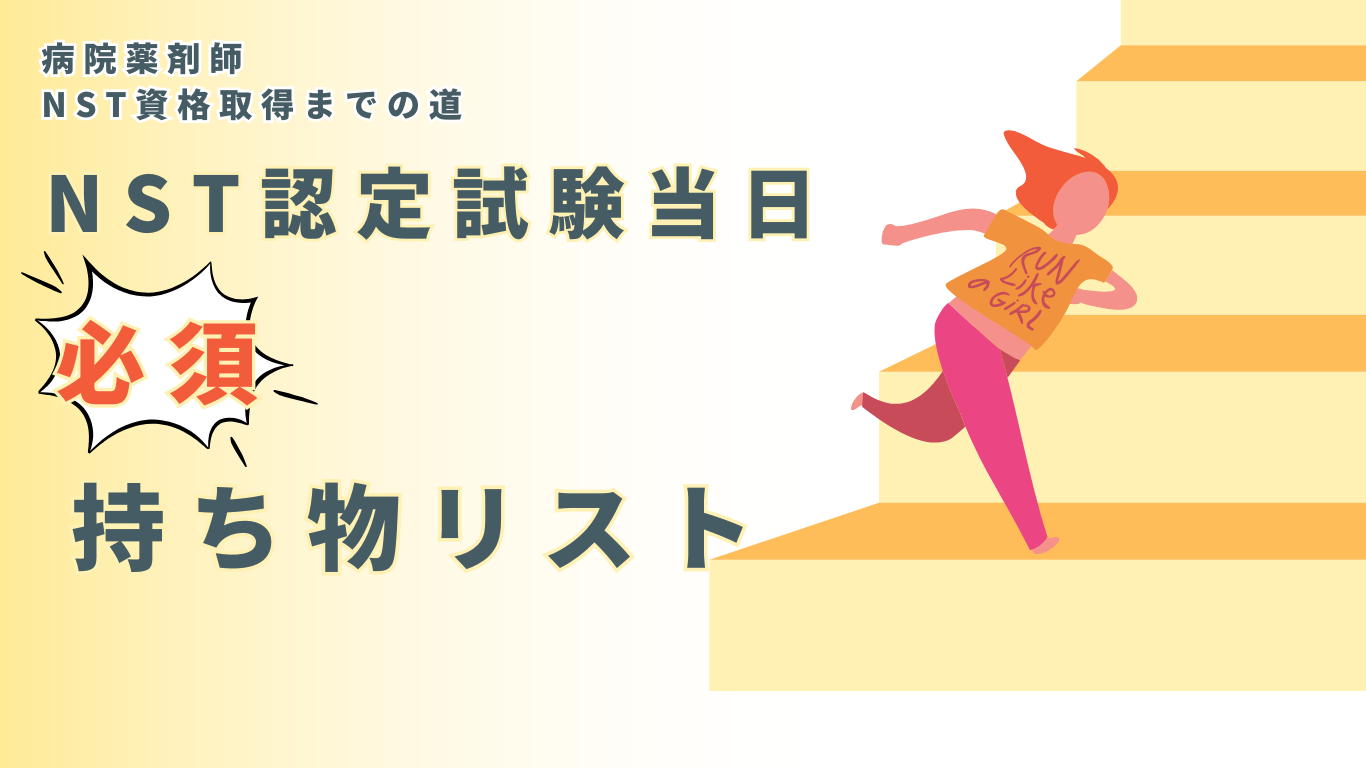【NST専門療法士試験対策】勉強方法と教材を紹介!仕事しながらでも大丈夫!

病院薬剤師のkeikoです。2024年にNST専門療法士の試験に合格した経験を生かし、NST専門療法士を目指す方に一人でも多くの人に合格してもらいたいと思っています。
NST専門療法士の認定試験を受験する方に向けて、仕事をしながらでも合格できる勉強方法を教えます。
これらの疑問にお答えします!
では、具体的にどのような教材を使って、どのように勉強していったのか、実際に何時間くらい勉強したのかお伝えします!
合格するための必要な教材
過去問題集
日本栄養治療学会JSPEN NST専門療法士認定試験過去問題集 2025年発行
正直、新しい過去問題集は発行されないと思っていました←
私の場合は2024年受験のため後に載せた2016年発行しかありませんでしたが、
それでも過去問題集の内容・解説から試験でも多く出題されていました。
今から受験する人は、まずは上記の2025年発行の過去問から始めてみてください。
導入はこの教材から学んでいくことが効率的で、全体で問われる傾向がわかると思います◎
そして、関連するところを3)のJSPENテキストブックで補足、情報更新するのがおすすめです。
※以下、2026年発行版は参考までに載せておきますね。
日本静脈経腸栄養学会 NST専門療法士認定試験 過去問題集Ⅰ 2016年発行
※日本静脈経腸栄養学会:現、日本栄養治療学会
基本問題集
日本静脈経腸栄養学会 認定試験基本問題集 2012年発行
※日本静脈経腸栄養学会:現、日本栄養治療学会
基本問題集だからと、これから問題を解こうとすると内容が細かいので、勉強期間が短い人へはおすすめしません。最初にこれから解き、解説まで理解しようとしたら、全然進まなくて萎えました・・・。
内容を深掘りできるので、1)の過去問題集の後に解くことをおすすめします。
2012年発行と古く、回答が間違っていることもあるため注意が必要です。
南江堂の書籍HPでは正誤表が公表されているので、購入後まず修正しましょう。(それ以上に間違えがあることもあります)
1)の過去問題集と同様、関連するところを3)のJSPENテキストブックで補足、情報更新するのがおすすめです。
JSPENテキストブック
日本臨床栄養代謝学会 JSPENテキストブック 2021年発行
過去問題集、基本問題集の関連するところの補足、情報更新に使用しましょう。このテキストブックはある程度の頻度で更新されているので信用できる教材です。
4.NST専門療法士受験必須セミナー【オンライン受講テキスト】 余裕があれば
私は2022年にこのセミナーを受けており、内容ははっきり言ってほとんど覚えていませんでした。
1~3を使って勉強しているときに、理解が難しい範囲を補足的に開いてみたりしましたが、ほとんど使えませんでした。後述していますが、まだ勉強していない分野を見つけるために使いました。勉強していない分野はテキストブックで補足しました。
5.メディカルスタッフのための栄養療法ハンドブック
他のテキストと違って、持ち運びできるサイズです。
そのため、通勤時間に勉強できるのが便利でした。
1タイトル毎に図や表でまとまっていて、とても簡潔にわかりやすいです。
頭を整理するのにおすすめです。
また、試験勉強だけでなく、臨床現場でパッと調べたいときにも使える代物です!
解剖から、スクリーニング方法、経腸栄養・静脈栄養、各病態別の栄養療法などNST試験の出題範囲はもちろん、臨床でも活用できそうな経管栄養不適医薬品や食事摂取基準、経腸栄養剤の一覧など栄養に関するものを網羅しています。
おすすめ勉強方法
過去問題集 +テキスト補足
基本問題集 +テキスト補足
過去問題集と基本問題集の2周目
5択1問のところ1問1答で解いていき、わからなかった・間違えたところに付箋をつけます。そのとき直前にもう一度見返したいところにも付箋をつけます。
過去問題集Ⅰと基本問題集の3周目
付箋を貼ったところだけ見直します。時間があれば間違えたところを何周かくり返し解きます。最終的に、設問と解説理解ができていればOKです。
5.話題の分野
1~4で過去問題集、基本問題集の設問と解説理解ができたら、テキストブックの目次を見て、ここ数年で話題になっているところを学ぶことがおすすめ。
例えば、「在宅栄養」「半固形栄養剤」「肥満症」「簡易懸濁法」「重症病態」「ERAS」「GLIM基準」などを追加で勉強しました。正直なところ、2024年試験にはこれらに関する問題も出題されました。令和6年診療報酬改定によって話題になった「GLIM基準」は2問も出題されました。
6.NST専門療法士受験必須セミナー【オンライン受講テキスト】で補足
パラパラ見て、まだ勉強していない分野を見つけてテキストブックで補足。のように使いました。余裕があればで良いと思います。このパラパラ見て学んだところから3問、「生体インピーダンス法」「赤血球指数による貧血分類」「指輪っかテスト」について出題されました。
7.テキストブックで学んでないところを補足
テキストブックの目次を見て、全く触れていないなってところを見ます。これは本当に余裕があればでOKです。過去問や基本問題集でテキストブックを補足で使用していると、意外とそのままの文言が試験に出たりしたので、まずは過去問や基本問題集を解くときにテキストブックで補足することがポイントです。
~おまけ~ 栄養ハンドブックを活用
テキストや問題集を解いていて、頭の中を整理できない!という方は、この本を使うととても簡潔にまとまっているのでおすすめです。
通勤時間など隙間時間に復習するのにも、役に立ちました。
勉強時間
この教材を使った勉強方法で、仕事をしながら2ヶ月半しかない中で勉強し、合格することができました。
仕事しながらって一体具体的にはどれくらい勉強の時間勉強にあてていたか、ということですが・・・
休日 :5~6時間
休みは多めの職場で25日くらいあり、そのうち20日くらいは予定もなく5~6時間勉強の時間にあてることができました。
仕事後 :2~3時間(週2回くらい)
仕事後はマックやカフェに寄って週に2回くらい勉強していました。残業や家事のこともあり週2回くらいが限度でしたね。カフェに寄れない日は30分~1時間くらいは家でも問題集やテキストを開いてました。・・・が、眠くなってしまい頭に入っていたかは怪しかったですね。
夜勤の入り前、明け日:3時間くらい
通勤時間 行き30分、帰り0分
試験2~3週間前あたりから復習するのに使ってました。間違えたところの付箋を貼ったところの見直しなど通勤時間の電車内で見ていました。勉強始めた頃は問題集だけでは理解が難しかったのでできず。帰りの電車は仕事で疲れているので、カフェでの勉強に備えて休んでました。
さいごに
テキストブックを1から読むことは無理・・・だし、私は読んでいたとしても覚えていられません。
この時間をかけて勉強方法1~3までは試験の2週間前までやることができました。
その後4~7を試験までできるところまでやりました。皆さんのご参考になれば嬉しいです。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45c8f322.c2831f9c.45c8f323.8989c0ab/?me_id=1213310&item_id=21649652&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8721%2F9784524218721.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45c8f322.c2831f9c.45c8f323.8989c0ab/?me_id=1213310&item_id=17855350&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8192%2F9784524258192.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45c8f322.c2831f9c.45c8f323.8989c0ab/?me_id=1213310&item_id=15961107&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9747%2F9784524269747.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45c8f322.c2831f9c.45c8f323.8989c0ab/?me_id=1213310&item_id=20296733&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8850%2F9784524228850.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45c8f322.c2831f9c.45c8f323.8989c0ab/?me_id=1213310&item_id=21179727&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6841%2F9784524206841.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)