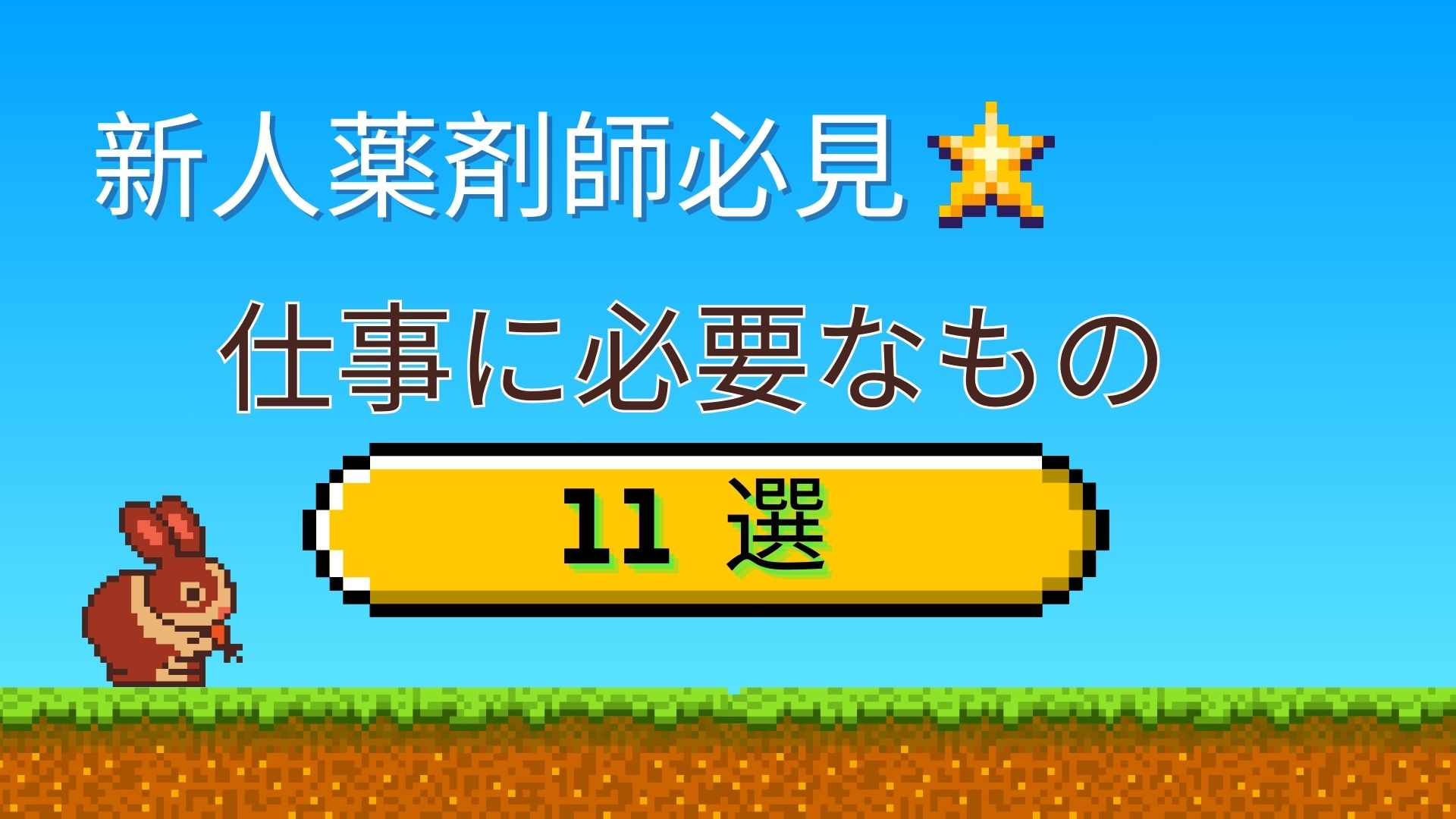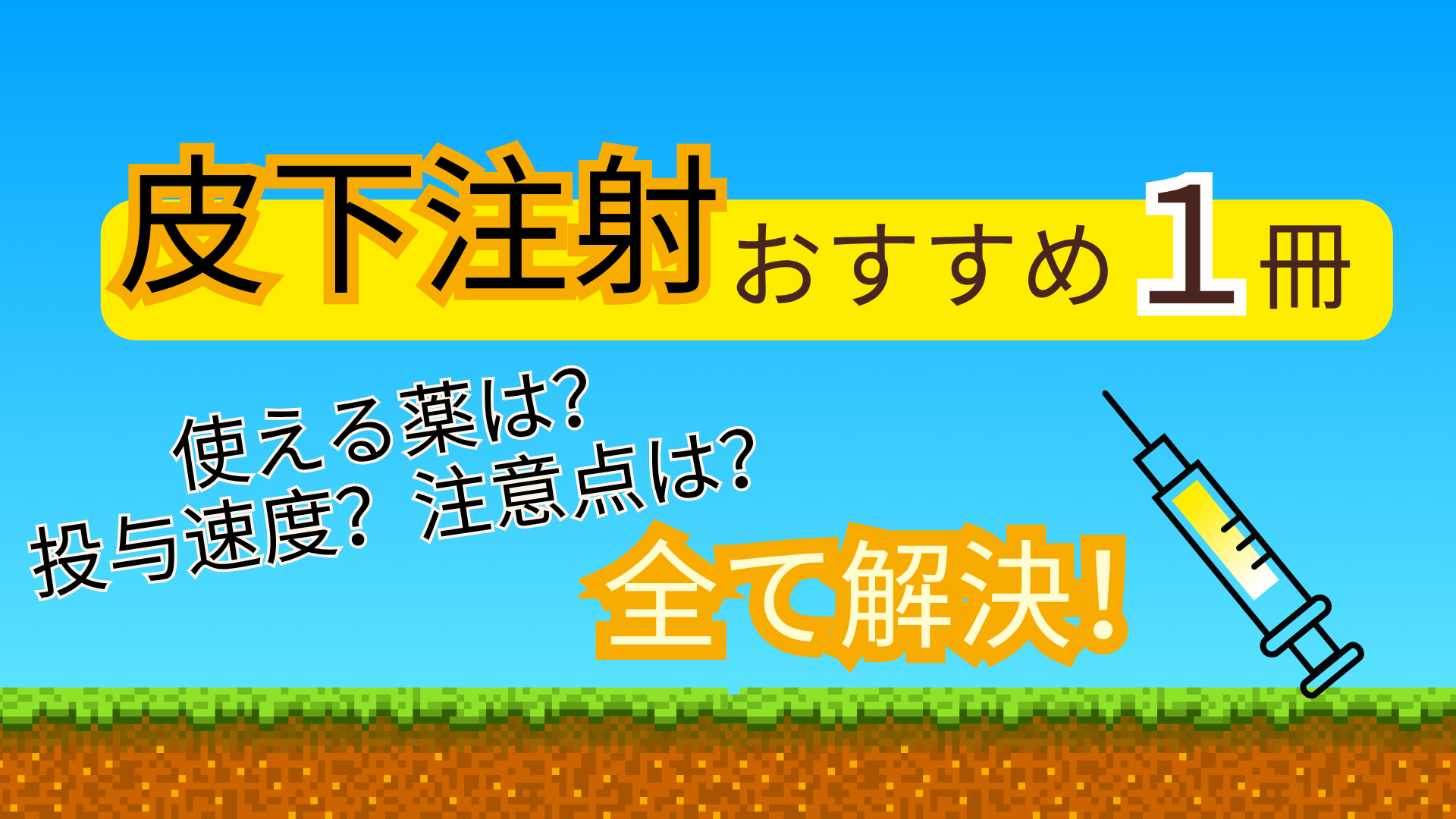【若手病院薬剤師必見】1,2,3年目の勉強方法・目標設定をしよう

社会に出てからの膨大な量の勉強方法はだれも教えてくれません。
それでも、業務をこなせるようになってしまうんです。
そのままでは、全体を「なんとなく」知ってるだけで
スペシャリストはもちろん、ジェネラリストにもなれません!
私は7年目の病院薬剤師。総合病院で一通りの診療科を担当してきました。患者さんにも医師・看護師にも、仕事をしているだけでは答えられないたくさん質問を投げかけられてきました。時には勉強不足でつっこまれましたが、負けじと勉強を繰り返してきました。
そこでこの記事では
「なんとなく」で終わらせない、若手薬剤師の勉強方法をまとめました。
「まず何から」始めたら良いかわかります。
7年目の私が今でも、役に立つ知識の身につけ方をまとめました。
勉強の仕方に悩んでいる方、なんとなく仕事をこなすだけになっている方は最後まで読んでください。
まずは「テーマ」を決めよう!
自分で分かりやすい、小さいものにする
最初は、本当に小さいテーマで良いんです。
調剤業務がメインで、まだ薬の知識がほとんどない状態だったら、
調剤する薬のコレだけは調べるっていうのを決めるんです。
- 配合変化
- 代謝経路
- 相互作用
- 腎機能に合った用量調節 等
次の一歩は、薬の知識を臨床に。テーマを少し広げます。
私がやりがちだったのは、「抗菌薬」とか「オピオイド」とか。
こんな大きな範囲だと勉強するのにとっても時間がかかるし、実際に活用できないんです。
だから、1つの処方箋を捕まえて
- 「抗菌薬」だと広すぎるから
→ 整形外科の手術の予防的抗菌薬
市中肺炎で使う抗菌薬 - 「オピオイド」だと広すぎるから
→ 緩和の疼痛コントロールで使う経口オピオイド
経口から貼付へのオピオイドスイッチング - 「便秘薬」
→この患者さんにとっての推奨便秘薬
難しく見えるかもしれませんが、自分でなんでもいいからテーマを決めたらいいんです。
小さいテーマから始めると、考え方が分かるようになってきます。
そして、これを繰り返していくと大きいテーマにも強くなってきます。
例えば小さいテーマで
「整形外科の○○の手術の予防的抗菌薬」
と勉強すると
(内臓までいかず)皮膚を切って手術をする。
→手術で感染するのは皮膚にいる菌で感染する可能性がある。
→だから○○の抗菌薬を使うんだ。
このように
感染原因→起因菌→抗菌薬の選択
の考え方の流れをつかめます。
そうすると他の手術においても
「術後感染予防で使う抗菌薬」
に強くなりますし、
これで
「抗菌薬」
の考え方にも慣れてきます。
「期間」を決めよう!
1日、1週間、1ヶ月単位など決めればOK
テーマを決めたら、それに合わせて期間を決めます。
自分のできる期間であればなんでもOKです。
期間を決めるとこのようなメリットがあります
・テーマに集中できる
・飽きない
・テーマを変えていくので網羅的に勉強できる
私はシフトに合わせて期間を決めてました。
例えば
1年目の調剤業務メインのとき
今週は注射調剤のシフトだから
配合変化「2日間」、投与速度「2日間」みよーっと。
病棟あがりたてのとき
オピオイド導入患者さんがいたからテーマはそれに決めよっ
・導入で使用されたオピオイドが何か
・服薬指導では何を/どうやって伝えたらいいのか
・なにをモニタリングしたら良いのか 等
臨床に近づけた少し広いテーマにしたので調べることが多かったので
「1ヶ月」くらい時間をとりました。
とことん調べてみよう!
スペシャリストになるつもりで調べる
とことん調べるってなんぞや?
スペシャリストを目指してるんじゃないんだけど・・・
そう思うかもしれませんが
自分なりにとことん調べてみることが大切です。
若手のうちはとことん調べてもスペシャリストにはほど遠いことが多いです。
そのため
決めたテーマを、期間内で
スペシャリストになるぞ!
といういきおいで勉強した方が良いと思います。
先ほどの例にあげたテーマでいうと、
整形外科の手術の予防的抗菌薬については、何を聞かれてもOK!
というくらい自信を持てるくらいに!
知っているよっていうことも調べてみる
「答え」は合ってるけど
・「理由」が違っていた、知らなかった
・こうやって「応用」されているんだ
ということもあります。
先輩から「その薬は△△だよ」と教わったことも
一度は自分で調べるようにしています。
知識が定着しやすかったり、根拠がわかるからです。
次のステップで紹介していますが、本を選ぶとき
先輩に教わった答えが載っている本を探すようにしてました。
本・論文を使ってみよう!
本を買ってみる
テーマに合わせて本を買ってみるのはおすすめです。
ネットでは
様々なところから調べないといけませんし、
自分が調べなければ検索にひっかかりません。
本なら当たり前ですが、まとまっています。
自分で疑問に思わなかったところも臨床で使えることが載っています。
薬、医療の内容って、ネットに載っていないことがあります。
ガイドラインなんかも、ネットから拾えるもの、そうでないものがありますね。
私がこれまで勉強してきた本でおすすめもご紹介していくので
気になったら買ってみてくださいね。

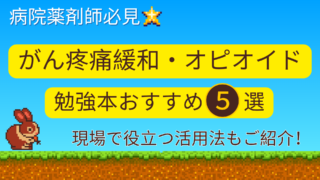
論文の「はじめに」を読んでみる
論文って抵抗があると思いますが
日本語論文で良いので「はじめに」を読むだけでも知識がグンッと増えます。
ここには、その論文の研究の「前提の情報」が載っているからです。
知らなかった!っという情報があって、結構面白いと思って読んでました。
しっかりしたエビデンスを探すのは、Pubmedが良いと思いますが
勉強、知識のとっかかりでは、Google Scholar(グーグル スカラー)がおすすめです。
無料の学術論文が載っており、Google検索のように気軽に検索できます。
つまづきポイント
疾患から勉強して失敗→薬から勉強する◎
薬剤師なんだから、薬剤師らしく
「薬から」勉強する
疾患から勉強しようとすると、“今” 活用できる知識を得るのに時間がかかります。
病棟業務をそろそろするから、疾患の勉強をしようかと思った1年目の私。
処方箋によく書いてあった「胆石症」から勉強をしてみました。
しかし私にとっては薬と関係が薄いところの範囲が大きすぎました。相当な時間がかかったわりに、すぐに臨床に活用できる知識を身につけることはできませんでした。(いざ、病棟にあがったときには忘れてしまっていて二度手間に・・・)
「ウルソデオキシコール酸」→「胆石症」で調べていくと良いです。
なぜなんとなく仕事をこなしてしまうのか
- 業務ができてしまっているから
- なんで?を追求していないから
実際に先輩から言われた言葉
・「業務をこなすだけだったら、慣れれば誰でもできる。」
・「患者さんのためを考えて、介入しようと思うと難しい。すごい知識が必要。今あなたの病棟に私が配属したら、もっとこうした方が良いって提案できる。」
こう言える先輩がかっこいいって思う反面、私自身が仕事をこなす薬剤師にならないかプレッシャーを感じました。そのおかげで、もっと患者さんのためにできることはないか?と一歩立ち止まって考え、深掘りしていくようになりました。
結果、それが薬の知識を臨床につなげられます。
まとめ
1~3年目薬剤師のおすすめ勉強方法
- 自分で分かりやすい、小さい「テーマ」を決める
- 自分で無理なくできる「期間」を設定する
- とことん調べる
- 本を買ってみる、論文の「はじめに」を読んでみる
自分にできる範囲のテーマや期間を決めて、目標設定することが大切です。
初めて見る薬や処方箋、自分が介入しやすい患者さんについて
「その患者さんのために」を考えて一歩立ち止まると、必要な知識がたくさんあります。
最初はゆっくりで大丈夫です。「誰かのために知る」ことが、薬剤師の力になります。
あなたの学びが、明日の誰かの助けになりますように。