【新人病院薬剤師のレベル上げ6】採用品や発注ルール、薬価について知らないと困ること

病棟に出るようになると、
「この薬、なんで使えないの?」「なんで同じ薬出せないの?」
こんなふうに聞かれる場面が出てきます。
すぐに答えられますか?
実はそれ、中央業務をしているうちに知っておくと答えられるようになることばかりなんです。
薬の採用品・発注の仕組み・薬価……
一見“裏方”っぽく見える内容が、臨床の場面でも重要な知識になってくるのが薬剤師の面白いところ。
この記事では、新人薬剤師が中央業務をしながら身につけたい「薬の扱い方」を、3つのテーマに分けて紹介します。
採用品を知る|まずは、薬の“区分”と“在庫ルール”を理解しよう
採用薬についておさえておきたいポイント4選
採用品とは、病院で使うことができる薬
調剤薬局では処方箋に書かれた薬は、基本的に取り寄せてでも調剤しなきゃいけないですよね。
病院では違います。
採用品ではない薬は、原則使うことができない運用になっています。
つまり 病院には病院の「使っていい薬=採用品」がある、というわけです!
- 採用品:院内で使うことができる薬
- 非採用品:院内で使うことができない薬
採用品には何がある?調剤や採用品リストから覚える
★同じ成分で剤形違いの採用品があるかな?
★自病院の採用品の調べ方を教えてもらおう
調剤で日常的に触れる薬や、薬品棚に並んでいる薬は「採用品」のはず。
調剤しているときに「あれ、この薬いつも処方出てるな」と感じる薬は、通常の採用品だと思って大丈夫!
採用品は「全て暗記しなきゃ!」と思いがちですが、パッと調べられる状態であればOK。調剤の数をこなしたり、薬品棚をみていると覚えていきます。まずはよく使う薬、病棟で頻出の薬から覚えていくのが現実的です。
薬の区分を知ろう!病院独自の薬の区分があることも。
実は、細かくこのように区分があることがあります。
- 臨時採用品:一時的に使うために採用した薬
- 患者限定で使用できる薬:特定の患者さん用に使うことができる薬
- 特別対応の薬:非採用品だけど、必要時に特別に購入する薬
この区分や運用ルールは病院によってバラバラなので、一概に説明できないのが痛いところです。
在庫ルールを知ろう!「採用品なのに、在庫がない!」なんてことも。
- 使用頻度が低い薬
- 薬価が高い薬
- 緊急性が低い薬
これらは採用品であっても、普段から在庫せず、都度発注する運用のこともあります。
患者限定で使用できる薬は、在庫をおいていないことが多いのではないでしょうか。
採用品の中に、さらに区分がある場合は要注意です。
ここも病院によって対応が違います。
- 医師から正式な申請書が必要な場合もある
- 電話1本や口頭依頼だけで対応できる場合もある
「自分の病院ではどうなってるか」を確認しておくのが大事!
申請してもらってから
発注→納品→払い出し
の流れや、払い出しまでどのくらいの時間がかかるのか確認しておくとベスト!
採用品を知ると、こんな問い合わせにも対応できる
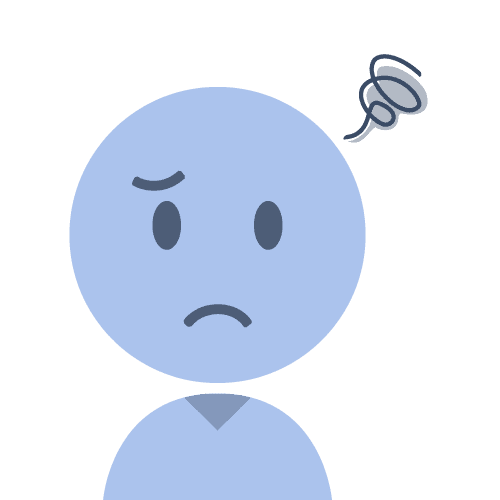
「採用なのに在庫ないの?なんで?」
採用だけど在庫を置いてない薬に対して、予め連絡をもらえないと薬を出せませんと伝えると、医師からこのように問い合わせがあることも。
→使用頻度が低く、緊急性が高い薬ではないので、連絡をもらってから対応する薬になっています。
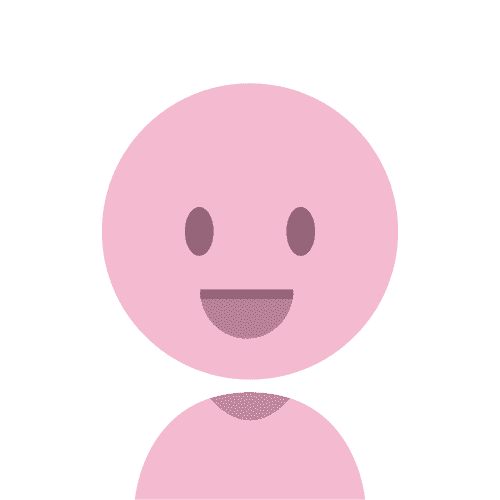
「いつも○○薬を飲んでいるんだけど、うちに採用ある?入院中も飲んでもらいたいから処方したいんだけど、処方できないんだよね。どうしたらいい?」
医師からこんな問い合わせも。
→採用品の中から代替薬を提案したり、患者限定薬だったら申請方法を伝えたり、代替が難しい場合は特別対応として薬を購入するか医師と相談することができます。
院内の採用品や在庫ルールを知っていると、このような問い合わせに対応できるようになります◎
実際にあったこんなこと
・「その薬は採用じゃないから、あっちの棚にあるよ。」
「その薬は採用だけど、おいてないから発注しといて。」
と先輩に言われ新人の私は混乱。正直、何言ってるの?って感じでした。
・カルボシステイン錠の粉砕指示があり、そのまま粉砕して調剤。あとから先輩に「ドライシロップが採用されてるのに、なぜつぶしたの?」と注意をうけた・・・
同じ成分が剤形違いで採用されていることを知っていると、無駄な粉砕をしなくてすみます。
明日からできる!採用品のワンポイントチェック
□自分の病院の採用品の調べ方は知ってる?
□病院独自の薬の区分があるか分かった?
□在庫を置いている薬、置いていない薬があった?
発注管理|薬が来ない!? 発注管理を知らないと困る話
発注→卸→納品のスケジュールを知ろう
いつも調剤してる薬はどこから、いつ薬局に入ってくるか知っていますか?
実は病院ごとに、薬の発注システムは異なります。
発注方法を知ると、在庫切れを防げる◎在庫がないときの対応ができる◎
通常業務では、発注担当薬剤師や委託しているSPD業者などが担当していることが多いです。どのように発注しているか、意識しないと気がつかないもの。
発注~納品までの仕組みを知っておくと
- 「この薬はいつまでに発注しなきゃヤバい」がわかる
- 必要なときに在庫が入らないということがないように対応できる
- 担当者がいないときにでも対応できる
- 医師や看護師に納品予定を説明できる
日常的にやるべきことは「よく使う薬か否か」と「今の在庫状況」の意識をもつ
「よく使う薬」と「動きが遅い薬」
調剤を重ねていくと、このように感じるようになってきます。
→「動きが遅い薬」が急に動き出したら、在庫が足りなくなる可能性があると予想できる◎
・あれ、在庫少ない?在庫切れになるかも
・急に必要になりそう
調剤しながらこのように感じられるようになれたら◎
→在庫のことであれ?と感じたら、事前に発注担当に相談・確認しておくことをおすすめします。在庫がなくなったとき、なんで調剤したときに相談しなかったの!と怒られないですみますよ。
実際にあったこんなこと
➊今日発注したら、明日入荷するよね!明日は土曜日だけど、いつも薬納品されてたし。
→しかし実際、以下のようにその薬の卸は平日しか納品していなかったので在庫がなくなってしまった。納品スケジュールを知らないと、必要なタイミングに薬が間に合わないことも。
| 薬 | 卸 | 発注時間 | 納品日 |
|---|---|---|---|
| A薬 | ○卸 | 金曜午前 | 土曜 |
| B薬 | △卸 | 金曜午前 | 月曜 |
➋緊急入院してきた患者さんの薬、在庫が少なくて今払い出したら明日分から足りないかもしれない。命にかかわる薬だから、医者に在庫がないとは言えない・・・どうしよう。
→緊急発注に対応できる病院であれば、その方法と納品スケジュールの知識が在庫切れを防ぐことができます。
➌A薬の処方が入った。薬局に在庫置いてない・・・どうしよう。在庫がないことを申し出たら、医師からいつからなら使えるの?と聞かれて、しどろもどろした。
→普段から「発注にどれくらいかかるか」を把握しておくと慌てません。医師や看護師にスムーズに情報提供できます。
明日からできる!発注管理のワンポイントチェック
□自分の病院の仕入れルート(卸・納品日)を確認した?
□よく使う薬と在庫の動きに気を配れてる?
□急に処方が増えた薬、在庫足りるか気にできた?
□緊急発注のルール、知ってる?
薬価|高額な薬は使えないことがある
薬価について、おさえておきたいポイント4選
病棟でよく出る○○薬、実は1錠あたり500円以上のものも!
「高っ!」と思ったあなた、薬剤師としての視点が1つレベルアップしています◎
病院薬剤師にとって「薬の価格=薬価」は、意外と大事なテーマです。
薬価を知ると、薬の取り扱いや適正使用、病院利益にも貢献できる
薬剤師はまず患者さんの健康・安全・適切な治療を最優先に考えます。
ですが、病院は「経営」も成り立たせなければ、医療を継続することはできません。
とくにDPC病院では、診断群分類によって1日あたりの入院費用が決まっていて、薬の費用も含まれています。
つまり、高い薬を使おうが、安い薬を使おうが、入院費用は変わりません。そのため、薬価が高い薬を多用すると、病院の「持ち出し」が増え赤字になることもあります。
(一部の薬は出来高算定できる場合もあります)
薬価を意識することで
- 高額薬を慎重に扱える(破損・紛失予防)
- 本当にこの薬でよいか?
「費用対効果」の視点での適正使用ができる - 医師に薬の価格について提案・相談できる
日常的にやるべきことは「高い薬」を意識すること
薬価を調べていると、この薬は安そう、高そうと予想できるようになります
まずは「この薬、高いんだよな」という感覚を持つことだけでもOK!
この“意識”があるだけで、実は業務のあちこちに良い変化が生まれます。
たとえば:
- 高額薬を調剤するとき、ミスや破損に自然と注意するようになる
- 「この薬で本当に処方合ってるかな?」と一歩立ち止まって判断できるようになる
- 在庫管理でも、過剰在庫に注意し、必要なときは先輩に相談できる
- 他職種(看護師など)に渡す際、高額なので取り扱いに注意してもらうよう一言添える
実際にあったこんなこと
・「高い薬だから入院中は使うことができないよ」って先輩に言われて衝撃だった。
・「この薬はめちゃめちゃ高い薬だから、紛失は許されないよ。だから薬局の外の人に渡すときには渡す側と受け取る側の印を押すルールになっているんだ」と言われて、取り扱いの違いを知った。
このように高額薬には、特別な取り扱いと責任が求められることがあります
明日からできる!薬価コスト管理のワンポイントチェック
□自分の病院の薬価の調べ方を確認した?
□よく調剤している薬は高額だった?
□高額薬を扱うときは、在庫・破損・取り扱いに注意できた?
まとめ
薬の扱い方について、いざ自分が困らないと興味を持ちにくい分野ですよね。ここでお伝えしたように、意外と大事な知識が多いです。普段の調剤で、薬の扱い方まで理解できるともっと薬剤師としての専門性を生かせていけます。
最後に、薬の扱い方について3つのことを振り返っておきましょう。
薬の扱い方について
- 採用品
→自分の病院で使える薬を把握し、薬の区分や在庫ルールを覚えよう - 発注管理
→発注~納品の流れを知り、在庫切れを予測・回避できるようになろう - 薬価
→高額な薬は注意!取り扱い方や病院経営にまで影響があるので意識して調剤しよう
知っているのと知らなかったのとでは大違い!対応力が全然違います!
少しずつ意識をして、自然に考えられるようになりましょう★





