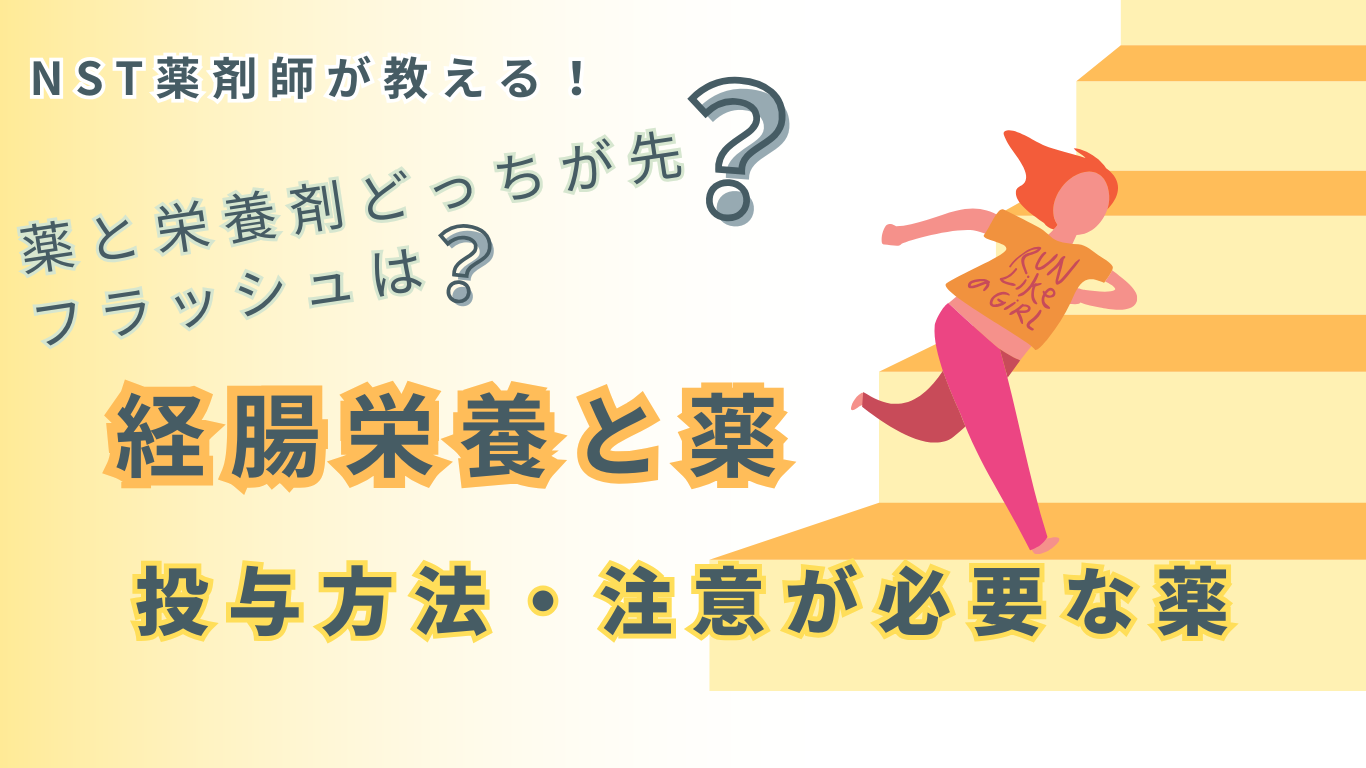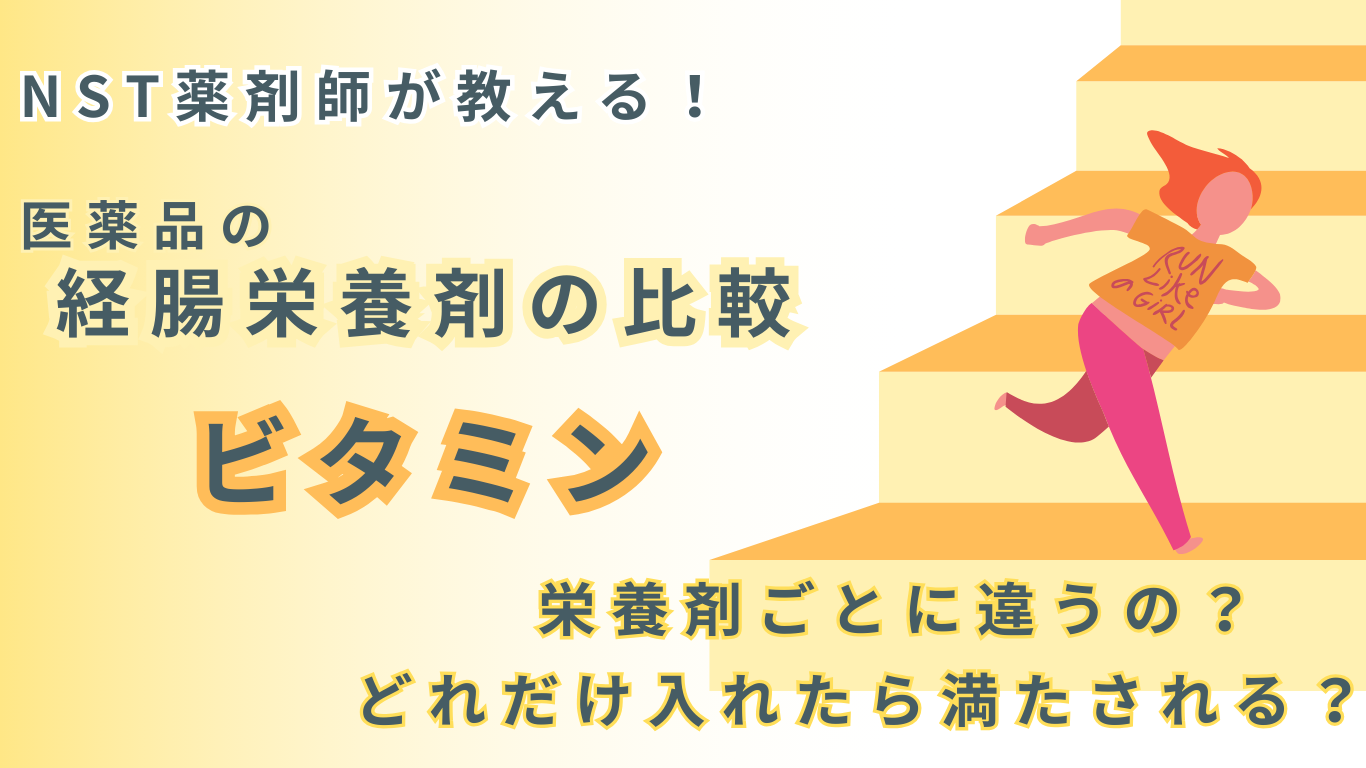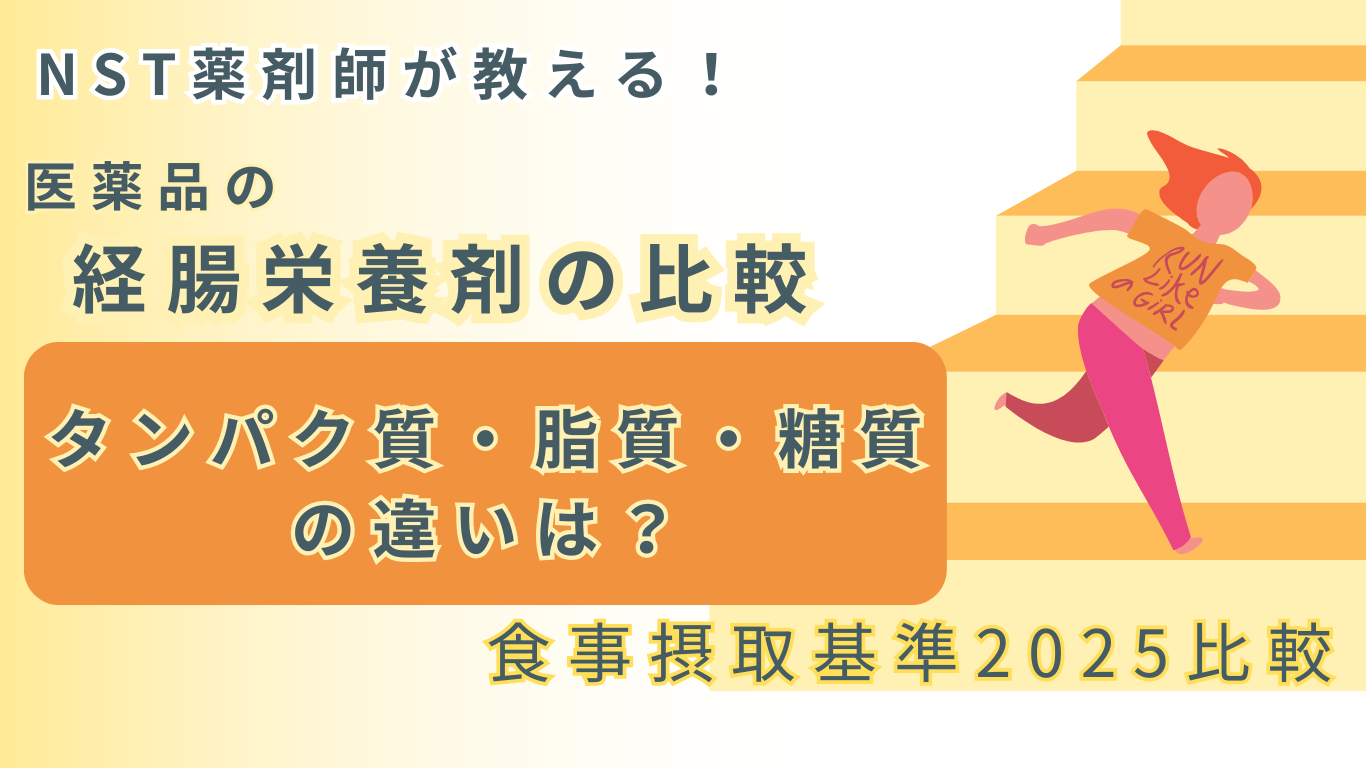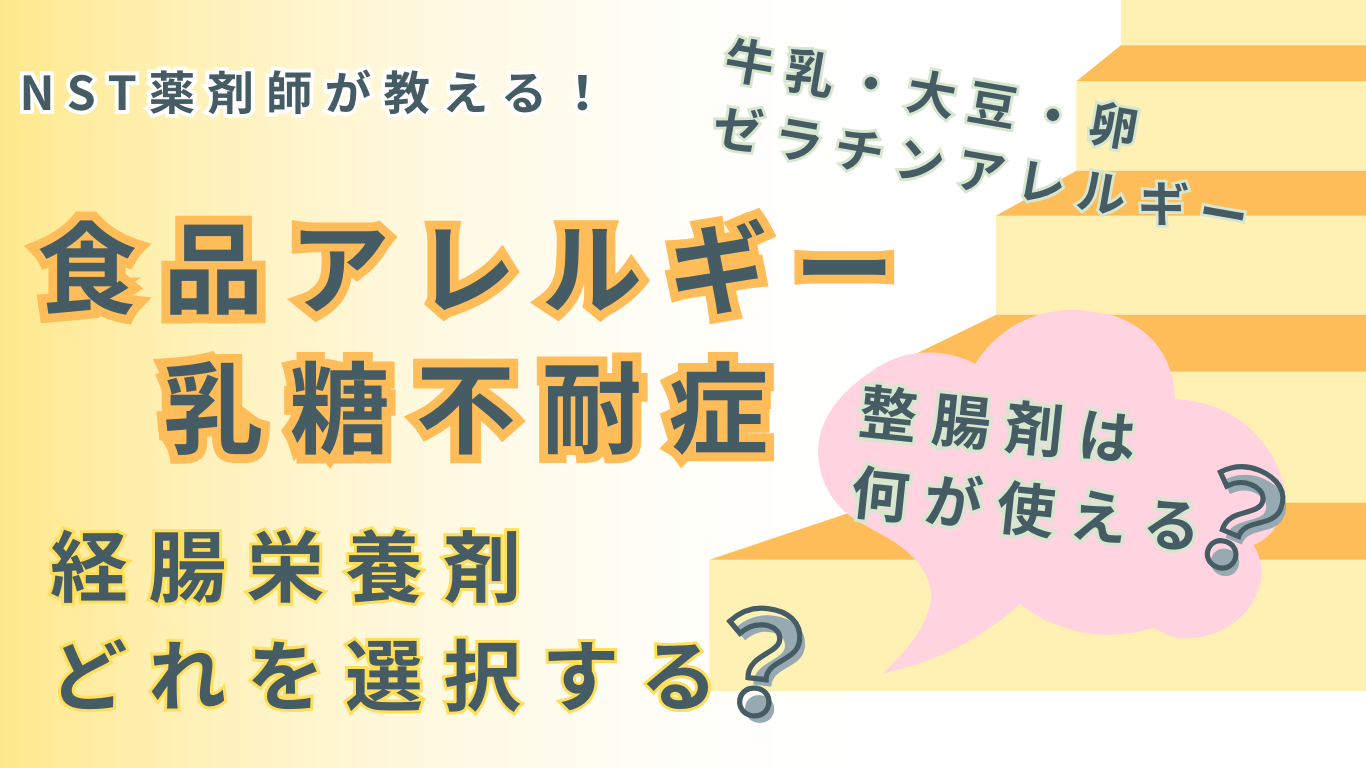経腸栄養剤における電解質の見方・選び方 NST薬剤師が教えるmg、mEq、食塩相当量の換算方法
NST薬剤師のkeikoです。
今回は私が経腸栄養剤を勉強し始めて、つまづいた電解質についての内容です。
薬剤師は普段の業務から、電解質は”mg”よりも”mEq”で考える癖がついているのではないでしょうか。K補充するなら、錠剤でも点滴でもアスパラギン酸カリウム等で補正し、そのときに気にする投与量ってmEqなんだよな・・・。点滴ならなおさら、投与速度や1日総投与量はmEqが基準になっています。
でも経腸栄養剤は”mg”で書いてある・・・
さらに!mgだけでなく、Naだったら食塩相当量とか書いてあるものもある!全部統一して全部書いて~~!と思う方いらっしゃいませんか?(私はそうだったので、誰か共感して欲しいです・・・笑)
そこで、私と同じように思っている方に向けて、
・”mg”と”mEq”と”食塩相当量”の換算方法、考え方
・実際の経腸栄養剤のNa含有量と1日に必要なNa量
・実際の経腸栄養剤のK含有量、腎機能低下者用の経腸栄養剤
についてご説明していきたいと思います。
1.mg→mEq換算方法
【結論】
mEq=電解質(mg)x価数 ÷ 分子数
分子量とか、価数とか大学では確かに習ったよ。でも覚えているわけないじゃん!という方。安心してください。栄養の範囲で使用する分子量と価数まとめました。なんなら、この換算係数を用いて計算したら早いです。
例えば、
Naは分子量が23、価数はNa+なので1(※CaはCa2+なので価数2)
Na(mEq)=1(mg) x1÷23=0.0435(mEq)
| 分子量 | 価数 | 換算係数 | |
| Na | 23 | 1 | 0.0435 |
| K | 39.1 | 1 | 0.0256 |
| Cl | 35.5 | 1 | 0.0281 |
| Ca | 40.1 | 2 | 0.0499 |
| Mg | 24.3 | 2 | 0.0823 |
意味を理解することも大事ですが、そこを覚えていても臨床では活用はできないし、これは覚えないとできません。だからこの換算係数をコピーして持ち歩くとすぐに換算できますね。他の勉強に時間を割きましょう!
2.Naと食塩相当量の換算方法
【結論】
食塩相当量(g)=Na(g)x2.54
※ここの単位は”g”です。お間違えないように。mgで表記されていることがあるので、適宜単位調整してください。
※食塩相当量からNaを求めたいときには順番を変えただけですが、この式に当てはめましょう。
Na(g)=食塩相当量(g)/2.54
ここは1で示した分子量の比を使って求めることができます。
なぜこれらの式になるかということを理解しておくと、計算式を無理に覚えておかなくても良いので一応ご紹介しておきますね。
まずNaと食塩相当量についてですが、
Na≠食塩(Naと食塩は別物)
食塩=NaCl(塩化ナトリウム)ということを前提にお話を進めていきます。
分子量はNaは23、NaClは58.5です。
分子量の比を使って計算すると、
Na(g):NaCl(g)=23:58.5
→NaCl(g)=Na(g)x58.5/23=Na(g)x2.54
となり、NaCl=食塩なので、食塩相当量はこの計算式になるわけです。
3.1日にNaはどのくらい必要か
【結論】
Naの基準はなし。
1日食塩相当量の目標量:男性7.5g 女性6.5g
※高血圧、慢性腎臓病、慢性心不全 6g未満
実はNaには基準となる量がありません。Naの代わりに食塩相当量で目標量が示されています。
食塩相当量は2025年日本人の食事摂取基準で上記の通りです。
余談にはなりますが、2021年の慢性心不全ガイドライン(正式には2021年 JCS/JHFS ガイドライン フォーカスアップデート版 急性・慢性心不全診療)では以下のようにご紹介されています。
”塩分制限の心不全の予後への効果については、明確なエビデンスが得られていません。本ガイドラインにおける慢性心不全患者の減塩目標は日本人の食生活の現状を考慮し1日6g未満とされています。ただ、高齢者においては過度の減塩は食欲を低下させ栄養不良の原因となるため、適宜調節が必要である”
また、高齢者では体内に塩分を保持するためのNa再吸収力が弱くなっており低Naのリスクがあります。入院患者の多くが低Naという報告もあります。
つまり、心不全患者で栄養摂取低下による体重減少傾向がある場合や高齢者にはNa制限はそこそこにした方が良いかもしれない。ということですね。
経腸栄養剤のNa含有量
【結論】
1000kcal 以下の投与では、塩分3g以下
※一般的には上記の通りですが、一方で高齢者のNa保持能低下に配慮したNa多めに含有している製品もあります。
以下、一部医薬品の経腸栄養を食事摂取基準に合わせて、”食塩相当量(g)”でまとめてみました。
| 食塩相当量(g) | 1袋あたり | 処方設計熱量あたり | 1000kcalあたり |
| エンシュア・リキッド | 0.5g | 3~4.6g | 2.2g |
| エンシュア・H | 0.8g | 3.8~6.9g | 2.2g |
| ラコールNF | 0.4g | 2.2~3.7g | 1.9g |
| イノラス | 0.7g | 2~3.4g | 2.3g |
処方設計熱量は添付文書に記載されている標準量あたりとしています。範囲の上値は、現実として投与するには難しい量ですが、その量でも1日食塩3~5gです。現実的に1日1000kcal投与したとすると2g前後になりますね。
普段の食事の補助的に経腸栄養剤を使用するならこの食塩の量はちょうど良いかもしれません。(日本食は塩分濃度が高いと言われていますし)
ただ、経腸栄養剤のみで栄養摂取をすると、塩分量が少ないため低Naになるリスクがあります。
上述しましたが、高齢者では体内に塩分を保持するためのNa再吸収力が弱く、低Naになりやすいので注意が必要です。
4.Na補正方法
経腸栄養剤のみではNaが低下することがあるということが分かったかと思います。
じゃあどうするのか?補正します。
【結論】
●チューブ使用時
十分量の白湯に塩化ナトリウム(NaCl)を溶解して投与する
●経口摂取できる時
食事中の塩分増やす→経口補水液を活用する、水に塩を混ぜて飲む
→塩化ナトリウム(NaCl)を処方してもらい服用、Na保持能低下に配慮した製品を使用
入院中であれば点滴で細胞外液やNa補正液を使用して補正されていることがよくあります。ただ、末梢がとれない。食事からのNaではNaが低下してしまう。など様々な理由でNa補正が必要な方がいらっしゃいます。入院中の食事でも言えますが、副食をほとんど摂取できず、主食メインだとNaはほとんど摂取されません。そのときもNa低下していないか注意が必要ですね。
そこで補正を考えたとき、このような発想がまず出てくるのではないでしょうか。
・経腸栄養剤に塩(処方では塩化ナトリウム)を混ぜる
・料理に処方された塩化ナトリウムを振りかける
・・・実はこれは×!!理由は以下の通りです。
【経腸栄養剤に塩を混ぜてはいけない理由】
①細菌増殖リスク
②沈殿、チューブ詰まりのリスク
そもそも”栄養剤”といっているだけあって、中は栄養がたくさん。ヒトにとっても嬉しい栄養ですが、細菌にとっても嬉しい栄養です。この出来上がった栄養剤に、無菌操作もせずに何かを混ぜると細菌増殖のリスクが高まり、感染対策の上で不可です。
また、塩分を混合すると沈殿して、チューブ(管)を使って投与する場合にはとくに詰まってしまうリスクがあります。すでに入っている塩分は平気なの?と思うかもしれませんが、製品は過飽和状態であることが多く、絶妙なバランスで作られています。(製作会社勤めではないので詳しくは分かりませんが・・・)そのためNaClを投与すると、その製品にとって過剰なNaがタンパク質が反応して塩析を起こしてしまい、固まってしまいます。
【料理に処方された塩化ナトリウムを振りかけない方が良い理由】
食欲低下、食事拒否につながる可能性がある。
調剤薬局では”塩化ナトリウム”として処方をみることもあるのではないでしょうか。自分で舐めたことありますか?普通の料理で使う塩とは違い、独特の味がします。よくあるのですが、この処方された塩化ナトリウムを食事にかけて一緒にとるという方は、あまり美味しいとは言えないでしょう。個人差があるかもしれませんので、絶対やめて!というほどではありませんが。せっかくの料理の味を低下させて、食事の量が少なくなってしまうということもあるので、ご注意くださいね。
口から摂取できる方は、食事中の塩分を増やすor経口補水液で対応できることが一番苦痛が少ないと思うので、おすすめです。
5.Kが少ない経腸栄養剤
Naの他に電解質でまず気をつけよう!と思う方、腎機能低下者の”K”に注目がいくのではないでしょうか。
【結論】
医薬品:腎機能低下者用の経腸栄養剤はない!
市販品:レナウェルA、レナジーbit、明治リーナレンLP、レナウェル3、
明治リーナレンMP、レナジーU
| K(mg) | K(mEq) | |
| エンシュア・リキッド | 370mg | 9.5mEq |
| エンシュア・H | 560mg | 14.3mEq |
| ラコールNF(液体) | 276mg | 7.1mEq |
| イノラス | 551mg | 14.1mEq |
| 市販の腎機能低下者用 の経腸栄養剤 | 10~30mg(※) | 0.3~0.8mEq |
※市販品にはK78mgのように、他より多めで食事療法基準に準じた値としているものもあります。
このように、医薬品では腎機能低下者用の経腸栄養ではないので、10倍以上Kが多く含まれているものが多くみられます。透析患者さんであったり、腎機能低下はあるけどKがあまりあがってこない方もいらっしゃり、低Kがみられることがあります。そのときには、腎機能低下者用ほどKが少なくありませんが、医薬品ほどKが多くないというものも市販で販売されています。採血結果のK値をみて調節しても良いのではないでしょうか。
以上、経腸栄養剤の電解質を勉強していく上で私がはじめに知っておきたいポイントでした。
皆様のお役に立つことができたら嬉しいです。