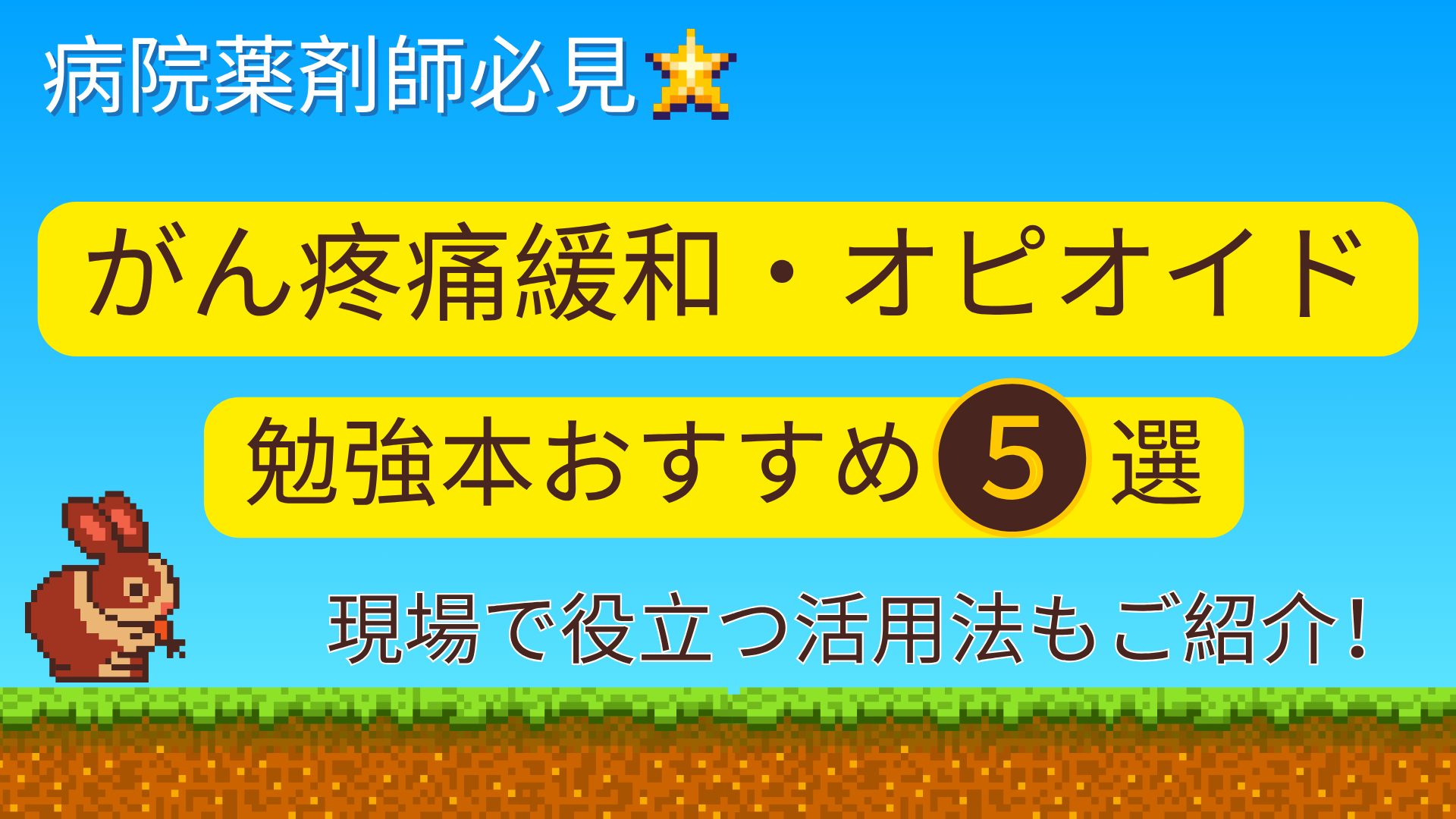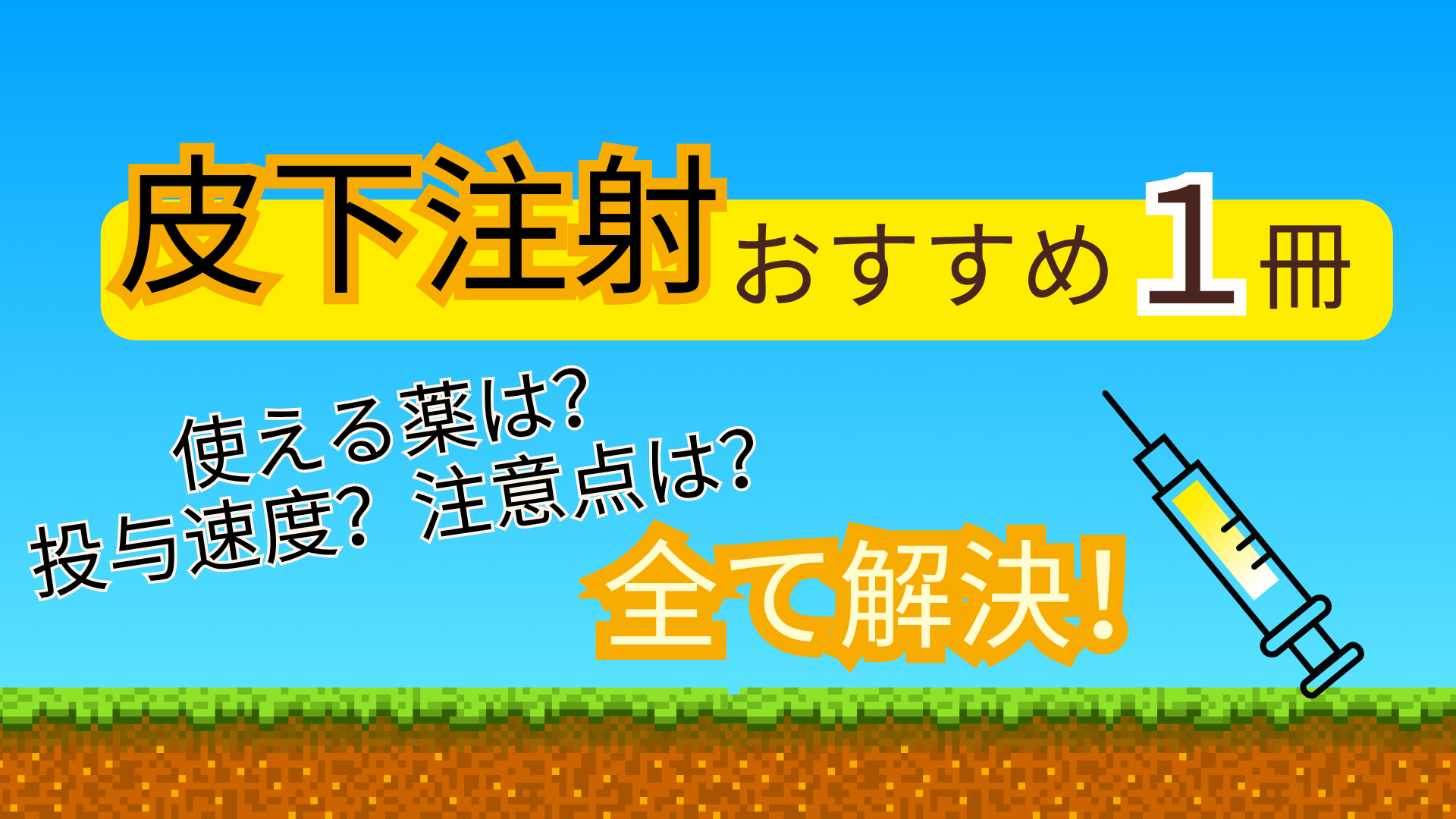【病院薬剤師必見】抗菌薬の勉強本5選!現場で役立つおすすめ活用法

こんなお悩みありませんか?
「抗菌薬」をいきなり勉強しようとすると
- 菌の種類が多い
- 英語で覚えにくい
- 薬の種類が多い
と量が莫大すぎて、何から、どうやって勉強していったら良いか分からない人が多いと思います。
私は7年目の病院薬剤師。総合病院で内科から外科系、循環器、泌尿器、婦人科まで幅広い診療科を担当してきました。
どの診療科でも薬剤師の介入が求められる場面が多く、質問もたくさん飛んできます。
抗菌薬は避けては通れないテーマです。
ただの暗記になると、キャパオーバーだし、臨床で使える知識が身につきません。
まずは考え方を身につけると◎
これらの本を使えば「抗菌薬」の理解はグッと深まります。
それでは、私が本当に役立ったおすすめの本を、使い方と一緒にご紹介します!
抗菌薬の勉強を始めるなら読むべき1冊
「抗菌薬の考え方、使い方」
ちゃんと勉強することが初めての方はおすすめ!
タイトル通り「抗菌薬の考え方、使い方」を学ぶことができます。
A5サイズ、602ページと分厚い本ですが、
初学者~中級者の方向けに、引き込まれる表現がされており、
抗菌薬の面白さを感じる1冊です。すらすら読めてしまいます。
薬剤師が知っておくべきなこと
作用機序から薬の効き方を考えたり、副作用や相互作用についてはもちろん書かれています。
臨床では、炎症があがったから抗菌薬を切るに切れない・・・という悩ましい事例も多くみられますが「抗菌薬をいつやめるのか」についても言及されています。
単に抗菌薬だけではなく
- 臨床で使える考え方や使い方
- 培養の取り方
- 抗菌薬を変更するときに見るべきポイント
など多岐にわたって解説されています。
活用方法
- 「学生,研修生のみなさんに,まずはここだけおさえとけば大丈夫,の10の掟」
まずはここを読んで、抗菌薬の「考え方」を学ぶ
→抗菌薬の勉強はつい理屈っぽくなりがちですが、「患者さんがよくなること」が本質。そういう視点を持つ大切さが書かれています。 - 抗菌薬の使い分けや特徴を知りたいとき
「ペニシリン系」「キノロン系」「抗真菌薬」 等
目次で検索して読み込む
→今日はこんな処方箋見たから、この薬の項目を読んでみよう。特徴がまとまっていて、なぜこの副作用が生じるのか、何に注意して使ったらよい薬なのか、を知ることができます。 - 「シナジー効果」「βラクタマーゼ」「MIC」など
ちょっと難しい言葉が出てきたら調べてみる。
→ちょっと難易度があがるけど現場で出てくる、これらの言葉も解説されていることが多いです。本をパラパラみて、この用語見たことがある!というだけでも強みになります。
この記事を書いている時にもう一度読みましたが、しばらく臨床経験した後でも学ぶことがたくさんあります。改めて素晴らしさを感じました。
培養結果から抗菌薬を選ぶ力をつけたいなら
「これでわかる!抗菌薬選択トレーニング」
培養結果から抗菌薬を選ぶ力を身につけるにはおすすめ!
症例ベースの問題が載っています。
培養結果、薬剤感受性結果、今の患者の状態から
- 抗菌薬を何に変更するべきか
- 変更する必要はないか
- 内服に切り替えるなら何にするべきか
といった薬剤師が実際に現場で考えることの多いことが問題になっています。
「抗菌薬一口メモ」もおすすめポイントです。
1症例に1つ載っていますが、知らなかった!という重要な情報がたくさんあります。
例えば、
薬剤感受性結果には“ S ”なのに、抗菌薬が効かない場合(内因性耐性)がある。
こんなこと知ってますか?私は読んで衝撃でした!
特定の菌種においては、内因性耐性をもつ抗菌薬では感受性試験をする必要はなく、感受性試験結果を載せる必要はありません。ただ、施設によっては感受性試験をして“ S ”とされるケースがあります。そのときは試験管内では効くと判定になってますが、臨床的には効かないと判断する必要があります。
活用方法
- 勉強する疾患を決める。→症例の診断名を見るor索引から調べる→端から解いてみる
→目次は「菌」ごとに症例がありますが、菌からよりも「疾患」で探して網羅的に学んでいくのがおすすめです。 - 「ある診断によって抗菌薬が投与されていて、培養結果待ち」
このような場面はよくあると思います。
→培養結果が出る前から、結果が出たらどうするか・・・と先手を打って勉強しておくようにしてました。上位の起因菌については症例があることが多いので、実際にそのまま使えるケースが多いです。 - 「抗菌薬一口メモ」を読んで、知識を増やす
培養結果からどのように抗菌薬を選択するか
について現場で使える知識を身につけるのに、この本は一推しです!
病棟でサッと調べられる持っておくべき1冊
「感染症プラチナマニュアル」(ポケットサイズ)
この本では
- 菌種、抗菌薬、疾患で索引できる
- 必要投与日数が載っている
- 投与量、腎機能調整量が載っている
- この疾患では、この検査を見ようとか、偽陽性のことが多い etc…
病棟で必要な情報が網羅されていて、仕事中に持ち運ぶならおすすめ!
最近は毎年情報が更新されています。情報が充実していて、ポケットに入れるにはだいぶ分厚くなりましたが、持ち運びにはもってこいの1冊です。
”Grande”と大きいサイズも販売されているので、お間違えないようご注意ください。
活用方法
- 医師へ薬の提案をするとき、この本を持ち運んでいれば
この本でも推奨されていますがいかがですか?と信頼度アップです。 - 抗菌薬の急な変更、培養結果が出たとき、病棟で急に相談されたとき
その場で調べて回答しやすいです。 - 抗菌薬の選択に迷ってASTの先輩に相談するとき
この本にはこう書いてあるのですが、この抗菌薬でよいと思いますか?
と漠然とわからない。ではなく次に生かせる質問ができます。
仕事中に抗菌薬を考えるときには、まず始めにこの本で調べるようにしています。
だいたいのことは解決するか、調べる手がかりをくれます。
仕事中に抗菌薬や菌種を調べるには、この本が必須です!
現場で使える治療の第一選択を調べるなら
「JAID/JSC感染症治療ガイド」
日本感染症学会・日本化学療法学会が作成しており、治療のガイドラインです。
- 16もの領域の感染症の概要
- 菌が特定される前のエンピリックにおいての抗菌薬の第一選択、次の選択肢
- よくある原因菌が特定された後の抗菌薬の第一選択
- 腎機能による抗菌薬の投与量
一つの基準として考えるのにおすすめの1冊です。
感染症プラチナマニュアルでは、抗菌薬の選択肢が載っていますが
これは順位づけされています。併せて見ると理解度が深まります。
最新版は2023年があります。以下の公式サイトから購入できます。
https://www.kansensho.or.jp/modules/journal/index.php?content_id=11
活用方法
- 「〇〇疾患に△△抗菌薬が処方された!この抗菌薬でよいかな?」
と調べるときに使います。
他の抗菌薬の方がよさそうなときは、日本感染症学会・日本化学療法学会で推奨されている第一選択は別の抗菌薬ですが、いかがですか?医師へ相談してみます。
術後感染予防で使う抗菌薬を調べるなら
「術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン」
- 投与タイミング
- 投与量
- 投与期間
- 診療科別に、具体的な手術の種類ごとに
選択する抗菌薬、アレルギーがあった時の選択肢
など術後感染予防の抗菌薬について
日本化学療法学会/日本外科感染症学会が作成しているガイドラインです。
サマリーのみはホームページで公開されています。
「術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン」で検索してみてください。
本は以下の公式サイト(日本外科感染症学会)で購入できます。
http://www.gekakansen.jp/antimicrobial-guideline_order.html
活用方法
- 手術予定で、点滴で抗菌薬が処方されている。この抗菌薬で合っているか?
- βラクタムアレルギーあった場合は何を選択すべきか?
- 術後何時間使うことが推奨されているのか?
これらを調べるときに使える1冊です。
医師からの問い合わせが多いのはβラクタムアレルギーがある場合です。
病院ではおそらく手術ごとにクリティカルパスが用意されています。通常はクリティカルパスで処方が入力されますが、アレルギーがあると医師は自分で抗菌薬を選択する必要があるため、問い合わせが多くなります。
ちなみに、クリティカルパスが完全にガイドラインを遵守しているケースは多くないと思います。なんらかの意向で決められているはずですが、一般的な推奨を知っておくことは必要です。
まとめ
抗菌薬のおすすめ勉強本5選!
- 抗菌薬を勉強を始めるなら
抗菌薬の考え方,使い方Ver.5 コロナの時代の差異 [ 岩田健太郎 ] - 培養結果から抗菌薬を選ぶ力をつけたいなら
これでわかる! 抗菌薬選択トレーニング: 感受性検査を読み解けば処方が変わる - 現場ですぐに確認できる本が欲しいなら
感染症プラチナマニュアル 2025-2026/岡秀昭【1000円以上送料無料】 - 現場で使える治療の第一選択を調べるなら
JAID/JSC感染症治療ガイド2019 [ JAID/JSC感染症治療ガイド・ガイドライン作成委員会 ] - 術後感染予防で使う抗菌薬を調べるなら
「術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン」
抗菌薬の勉強は、最初はとっつきにくく感じるかもしれませんが、目的に合った本を使えば確実に知識が身につきます。
ここで紹介した本は、私自身が現場で活用してきた実感のあるものです。
勉強の入り口として、そして日々の臨床での頼れる相棒として、ぜひ取り入れてみてください。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45c8f322.c2831f9c.45c8f323.8989c0ab/?me_id=1213310&item_id=20626766&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7181%2F9784498117181_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47e39a9b.2a418078.47e39a9c.95578e18/?me_id=1310259&item_id=10260112&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooksdream%2Fcabinet%2Fracoon_426%2F4260038915.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47e3b803.ace9fdf2.47e3b804.d40cf43d/?me_id=1285657&item_id=13016745&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01149%2Fbk4815731233.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45c8f322.c2831f9c.45c8f323.8989c0ab/?me_id=1213310&item_id=19810544&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3935%2F9784897753935_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)