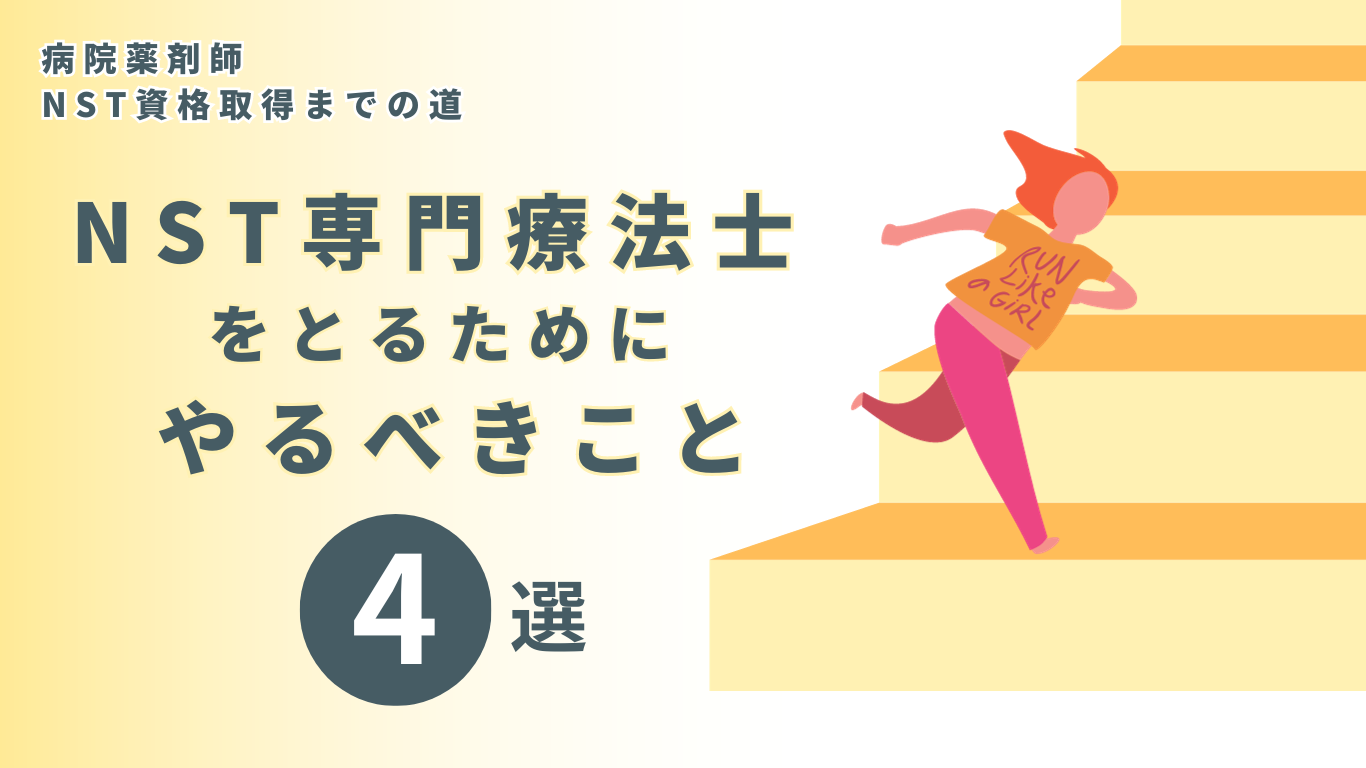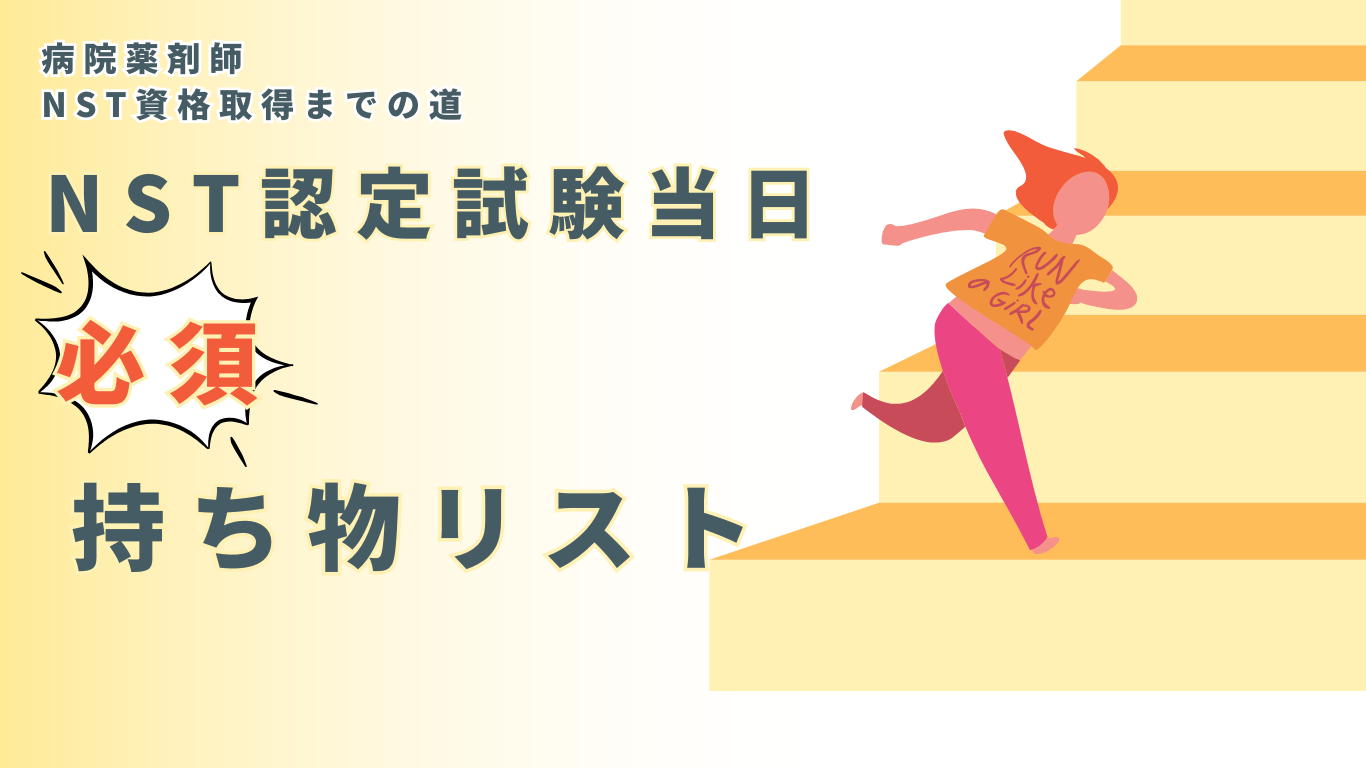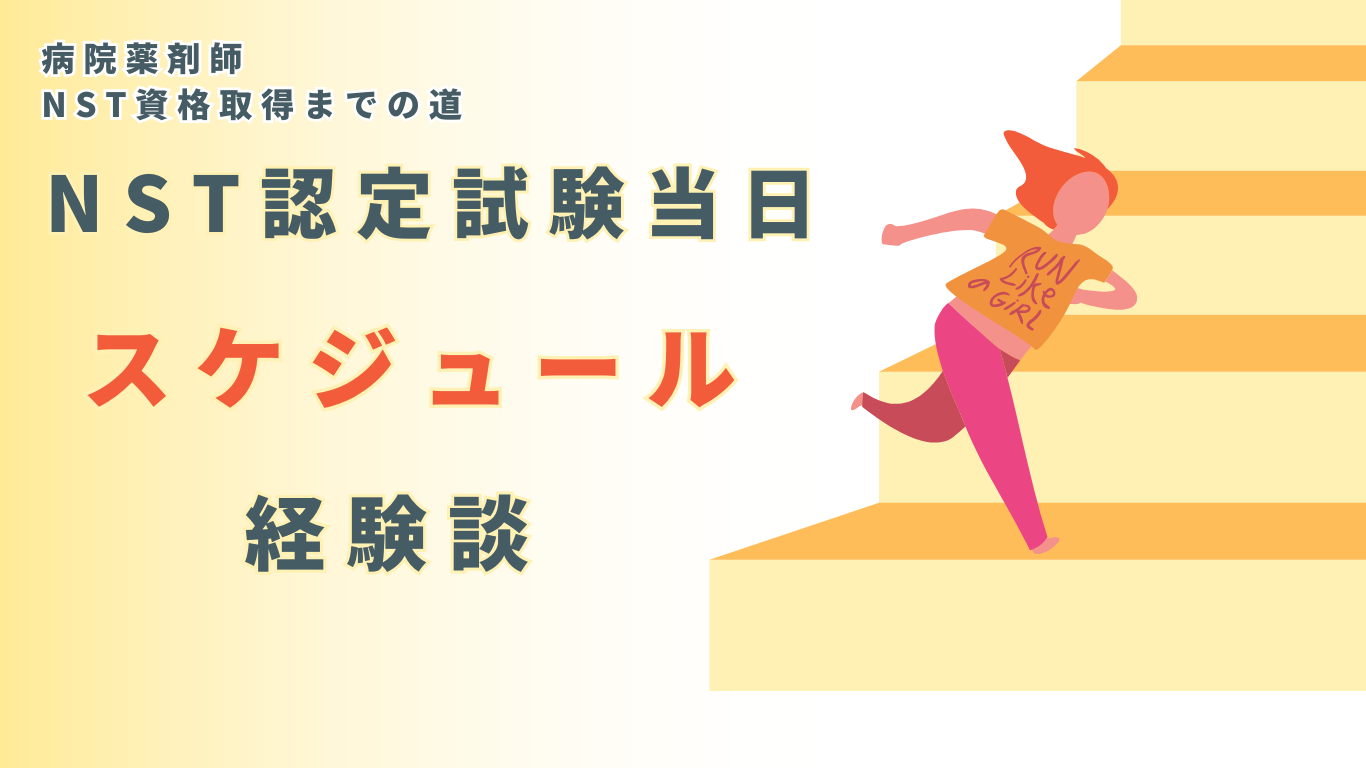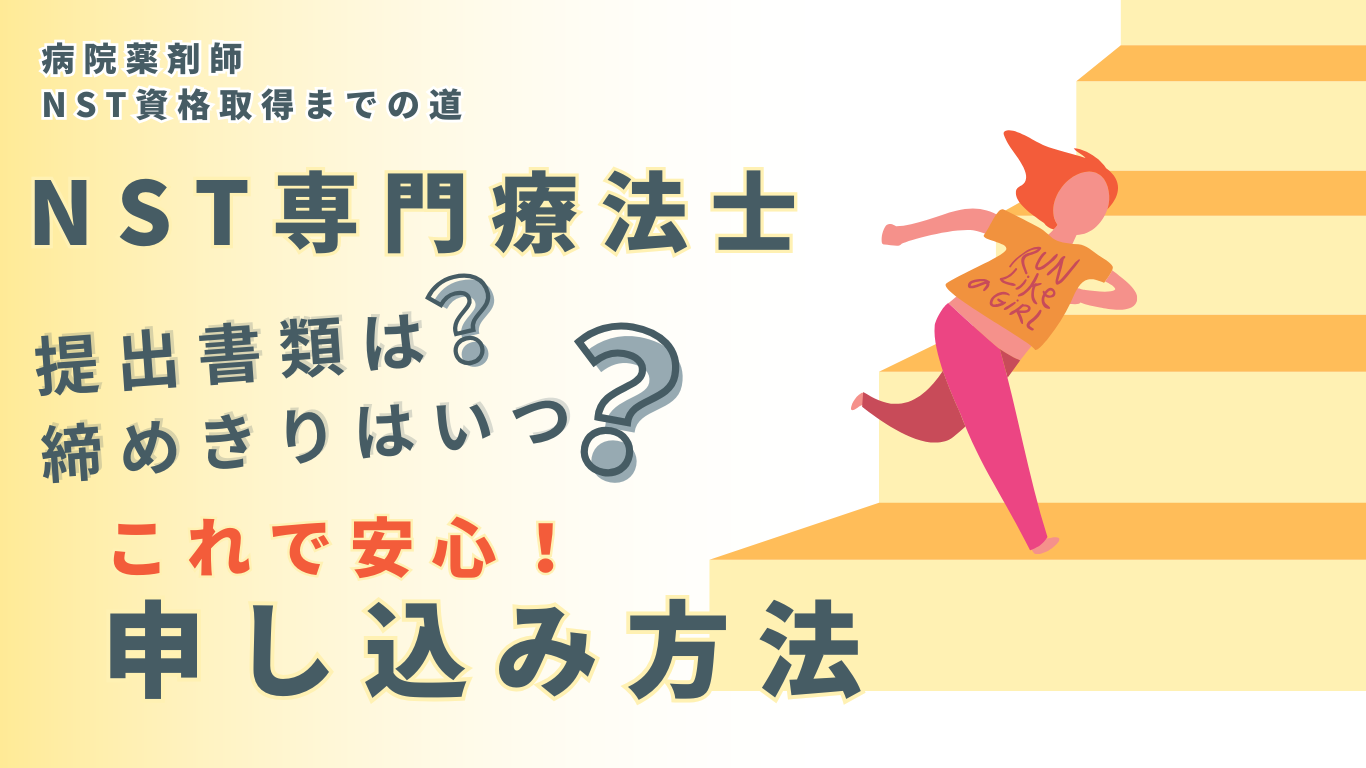NST専門療法士取得方法!試験までのおすすめスケジュール、最短でとる方法もご紹介
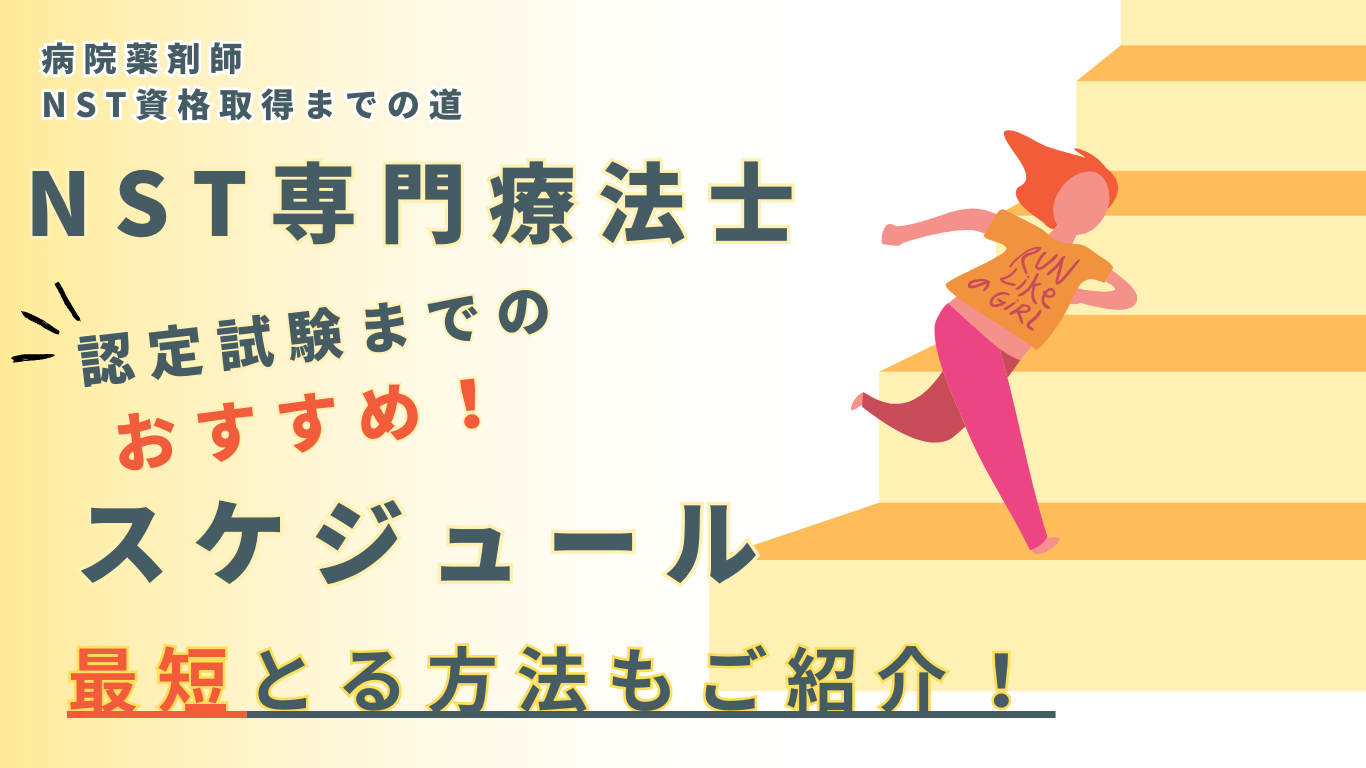
病院薬剤師のkeikoです。
2024年にNST専門療法士の試験に合格した経験を生かし、NST専門療法士を目指す方の役に立つような情報発信をしています。
私が資格をとりたいと思ったとき、今から資格をとるために時間は間に合うのかな?だいたいのスケジュールはどうなの?とたくさん調べました。資格をとりたいと思ったのは、臨床現場で役に立てるようになるためです。そのため、資格をとるためのスケジュールを調べるよりも、今は実践で役に立つような知識を身につけたい!勉強したい!という気持ちが強かったです。それなのに、スケジュールを調べることに時間を費やしてしまった・・・。簡単に、資格を取得するまでのスケジュールが分かれば、そんな思いはしなかったはず。そんな思いから、この記事を書いてます。
NST専門療法士になりたい!
・・・けど、どんな手順で何をやったら良いか分からない!
NST専門療法士の資格を今すぐとりたい!今やる気になったからやる気があるうちにとりたい!
・・・けど、一番早く資格をとるにはどうしたら良いの?
そんな方に必見です。
焦らずスムーズに資格をとりたい方 → おすすめルート
できるだけ最短で資格をとりたい方 → 最短ルート
をご参考ください。このルートで行えば、資格取得に必要な条件をクリアできます。
※2024年~国家資格取得後5年以上→3年以上になりました。(※○年目)は2024年までの国家資格取得5年以上の時に想定した年数です。
おすすめルート
2年目(※4年目)
受験必須セミナー受講 第1回 or 第2回 (オンライン)→2025年~e-larning
このセミナーをはじめの一歩として受講することをおすすめします。
理由は、以下の通りです。
・NSTについて基本的な内容の講義
・資格取得に必要な単位が獲得できる
・期間内であれば好きな時間に、何回でも受講できる
・講義資料がもらえる
新型コロナウイルス感染流行前の2020年までは現地で受講する必要がありましたが、それ以降はオンラインでの受講になりました。
・申込期間:2025年2月17日(月)10:00 ~ 11月30日(日)
・視聴期間:申込から60日間
※11月に申し込みしたら11月30日まで60日ないので、視聴期間は11月30日までとなります
このようにほぼいつでも受講できるようになったのは、
資格取得するため、勉強をはじめる第一歩として、さらにおすすめできるようになりました。
この仕様変更はうれしいですね。
※以下、必須セミナーの2024年までの情報です。記録として残しておきますが、読み飛ばしてOKです。
このセミナーはいつでも受講できるわけではなく、1年で2回募集がかけられています。
コロナ渦で多少ずれていましたが、最近は時期が安定しており、
第1回 受講期間:3月下旬~5月下旬(申込期限:2月中)
第2回 受講期間:6月~7月 (申込期限4~5月中旬)
が多いです。以下に過去の申込期限と受講期間をまとめえみたのでご参考ください。
過去の受験必須セミナー申込期限と受講期間
| 第1回 受講期間 | 申込期限 |
|---|---|
| 2024年3月25日(月)10:00 ~ 2024年5月24日(金)23:59 | 2024年1月29日(月)10:00 ~ 2024年3月 1日(金)17:30 |
| 2023年3月22日(水)10:00 ~ 2023年5月21日(日)23:59 | 2023年1月25日(水)10:00 ~ 2023年2月28日(火)17:30 |
| 2022年3月28日(月)10:00 ~ 2022年5月31日(火)23:59 | 2022年2月28日(月)10:00 ~ 2022年3月25日(金)17:30 |
| 2021年7月 1日(木)15:00 ~ 2021年8月31日(火)23:59 | 2021年6月 8日(火)10:00 ~ 2021年6月28日(月)17:30 |
| 第2回 受講期間 | 申込期限 |
|---|---|
| 2024年6月 3日(月)10:00 ~ 2024年7月31日(水)23:59 | 2024年4月15日(月)10:00 ~ 2024年5月13日(月)17:00 |
| 2023年6月 1日(木)10:00 ~ 2023年7月31日(月)23:59 | 2023年4月17日(月)10:00 ~ 2023年5月15日(月)17:30 (5月31日(水)17:30まで延長) |
| 2022年7月15日(金)10:00 ~ 2022年9月14日(水)23:59 | 2022年6月15日(水)10:00 ~ 2022年7月14日(木)17:30 |
| 2021年6月 1日(火)15:00 ~ 2021年7月31日(土)23:59 | 2021年4月23日(金)10:00 ~ 2021年5月24日(月)17:30 |
日本栄養治療学会(旧日本栄養治療学会)学術集会に参加(2月~3月)
まだ基礎知識がなければ、教育講演という基礎的な内容の講演もあります。
私は最初、栄養について知識がほとんどなかったので、教育講演をメインに探し、
薬剤師なので薬が関係しそうなところに参加しました。
栄養の学会ですが、がんの学会、集中治療学会、褥瘡学会などと一緒にやっている演題もあるので
臨床現場でよく見る疾患のところに参加しても良いですね。
3年目(※5年目)
臨床実地修練(40時間の実務実習)
早めに実習したい施設の条件や日程は確認しておきましょう!
施設によって時期も内容も異なっています。
人気施設だと以下の条件を満たしていないと、また次回申込してください・・・ということがあります。
・次の認定試験を受験できる資格取得後年数を満たしていること
(難しく言いましたが、つまりは3年目後半か4年目以上)
・受験必須セミナーを受講済み
私が実習した施設はとくに条件はなく、そのような施設が多いわけではなさそうです。有名な先生がいる施設だと応募が殺到している印象がありました。
日本栄養治療学会(旧日本臨床栄養代謝学会)学術集会 (2月~3月)
認定試験前の学術集会には参加しておくことをおすすめします。
理由は、最近のホットワードを知ることができるからです。最近のホットワードは認定試験でも問われていました。(例えば、GLIM基準、肥満治療・・・など)
4年目(※6年目)
試験勉強
3年目までに今まで記載した内容を済ましておけば受験する年は勉強に専念できます。
7月頃 認定試験申請
ここまで順調にやっていれば、余裕をもって申請できます。
※この頃には認定試験の日程や場所が確定していると思うので、遠方であればホテルや新幹線、飛行機の予約もできます。早割も使えそうですね。
10月 認定試験
いざ試験!当日の試験日程や持ち物をしっかり確認して臨みましょう。
※持ち物については別に記事があるのでご参考ください。
最短ルート
あくまで今からご紹介するのは、2024年度ではこのように取得できるよ。ということです。
今すぐにとりたい!今やる気がでているから、今のうちにできるだけやりたい!という方、私は思い立ったらすぐに行動すること多いですが、締め切りギリギリになってしまうことも多くチャンスを逃してきたこともあります。
各日程が変更になることもあるので、最新の情報を確認して申請期日など逃さないようにしてくださいね。
3年目(※5年目) 2月~3月
①JSPEN学会に入会する
学会やセミナーで学会会員だと参加費や受講費が若干安いので、最初に入会することがおすすめです。
②日本栄養治療学会(旧日本臨床栄養代謝学会)学術集会に参加【10単位】
最新のホットワードが何かみておくことがポイントです。何がなんだかわからなくても、抄録から”このワードが多く取り上げられているな”ということを覚えておくと試験に役立ちます。
③第2回受験必須セミナー申し込み
※2025年から申込期間と受講期間が変更になりました。ほぼいつでも受講できるようになったので、自分のスケジュールと相談して申込してください。
・申込期間:2025年2月17日(月)10:00 ~ 11月30日(日)
・視聴期間:申込から60日間
※11月に申し込みしたら11月30日まで60日ないので、視聴期間は11月30日までとなります
※以下2024年までの情報です
4月~5月中旬頃で申し込みの締め切りがあります。逃さないようにご注意ください。
おすすめルートの中でもご紹介しましたが、過去の受験必須セミナー申込期限と受講期間をご参考ください。
④臨床実務修練 スケジュール決め
認定試験申請の期日(7月頃)までにスケジュール修了する施設を調べ申し込み or 申し込みできる日程を調べましょう。
施設によって申し込み方法も期間も異なるので、早めにやることをおすすめします。
施設が決まってあまりに申請期日にぎりぎりでしたら、受験年に申し込み可能か念のため確認しても良いと思います。
⑤学会や支部会で10単位以上獲得するためのスケジュール決め
本当は2回学術集会に参加することが一番単位を満たしやすいですが、学術集会は1年に1回しかないのでもう間に合いません。(コロナ渦は時期がずれて1年に2回やることもありましたが。)
そのため、他の単位がもらえる学会や支部会に複数回参加して、少しずつ単位を取得する必要があります。
JSPEN学会のホームページの”支部学術集会”というタブがあるので、そこで参加できる日程から選びましょう。
3年目(※5年目) 3月 ~ 4年目(※6年目) 7月
①受験必須セミナー受講 【10単位】
だいたい6月~7月にあります。申請までに受講を完了する必要があります。
認定試験直前のセミナーになるので、記憶が新しいため試験には有利です。
おすすめルートの中でもご紹介しましたが、過去の受験必須セミナー申込期限と受講期間をご参考ください。
②臨床実務修練修了
最短ルートだとバタバタと忙しいと思いますが、他施設で勉強できる機会はめったにないです。
しっかり実習受けた方が自分のためにも、もちろん試験のためにも役立ちます。
※6月~7月に修了した方は、臨床実地修練猶予申請書を提出する必要があるかもしれません。確認してみた方が良いですね。
③支部会などで10単位以上取得完了
支部会などでは参加回数が多くなってしまいます。色々な場所で行われるので、お住まいによっては移動が大変かと思いますが、これはがんばるしかないですね。オンラインで参加できるところがあれば、それを選ぶのもポイントかもしれません。
④認定試験の申し込み 7月頃
今までのことを全て7月まで終えたら、すぐに申請書類をそろえて申し込みをしてください。きっと申請期日が間近だと思います。
4年目(※6年目) 8月~10月
試験勉強
このルートだと、試験勉強として時間がとれるのは8月からになってくると思います。
セミナーや実務修練など直近でやっているので覚えている知識も多いのではないでしょうか。
厳しいとは思いますが、可能であればセミナーを受講しながら過去問を説いたり、実務修練しながら関連するところを教材で勉強していると、より一層身につくと思います。
※この頃には日程や場所が確定していると思うので、遠方であればホテルや新幹線や飛行機の予約もしておきましょう。
10月頃 認定試験
いざ試験!当日の試験日程や持ち物をしっかり確認して臨みましょう。
最短ルートはお金や自分の負担もかかるのでおすすめはしませんが、
本気でスケジュールを詰めて、支部会の場所を選ばずやろうと思えばやれないことはないと思います。
ご紹介したルートでやっていただいていれば、初めにJSPEN学会に入会されていると思いますので、
学会から各種申請期日についてもメールが届きます。期日には敏感になっておきましょう。
参考:JSPEN学会ホームページ