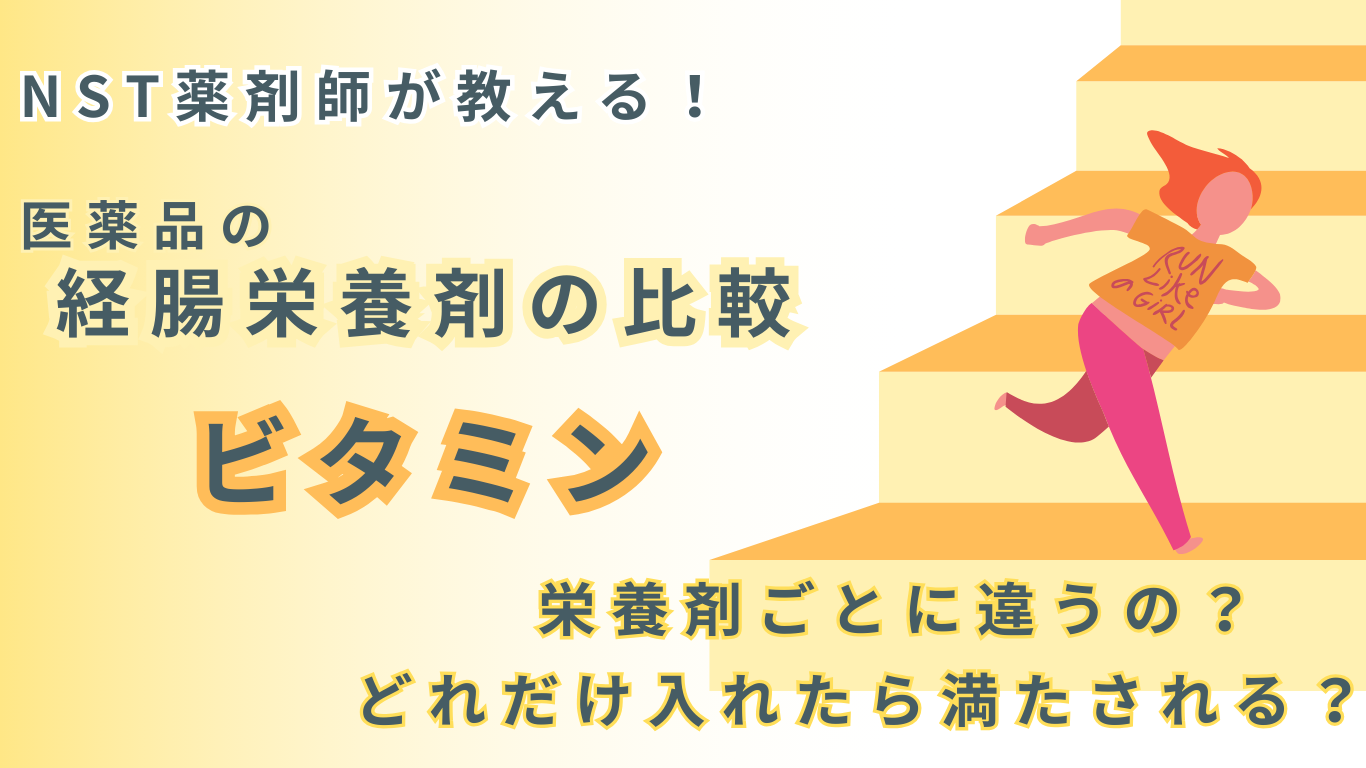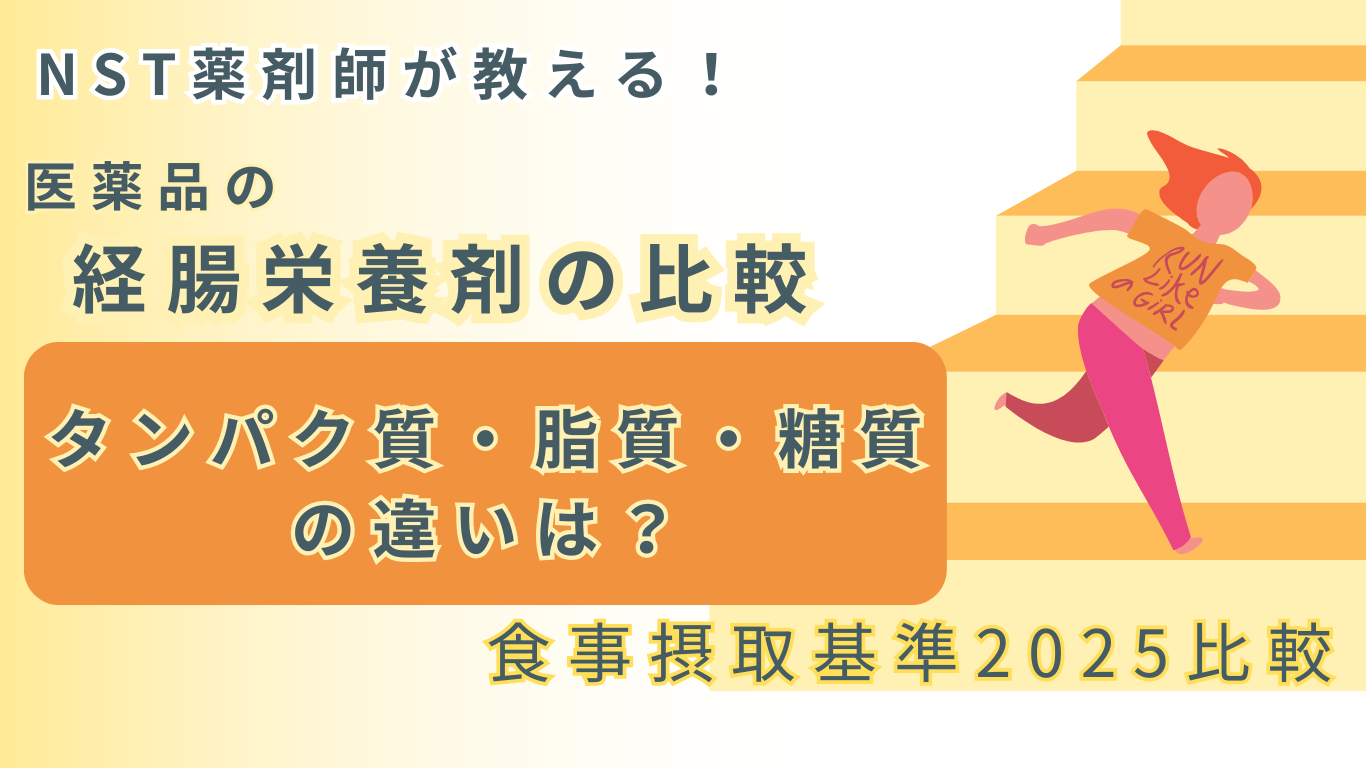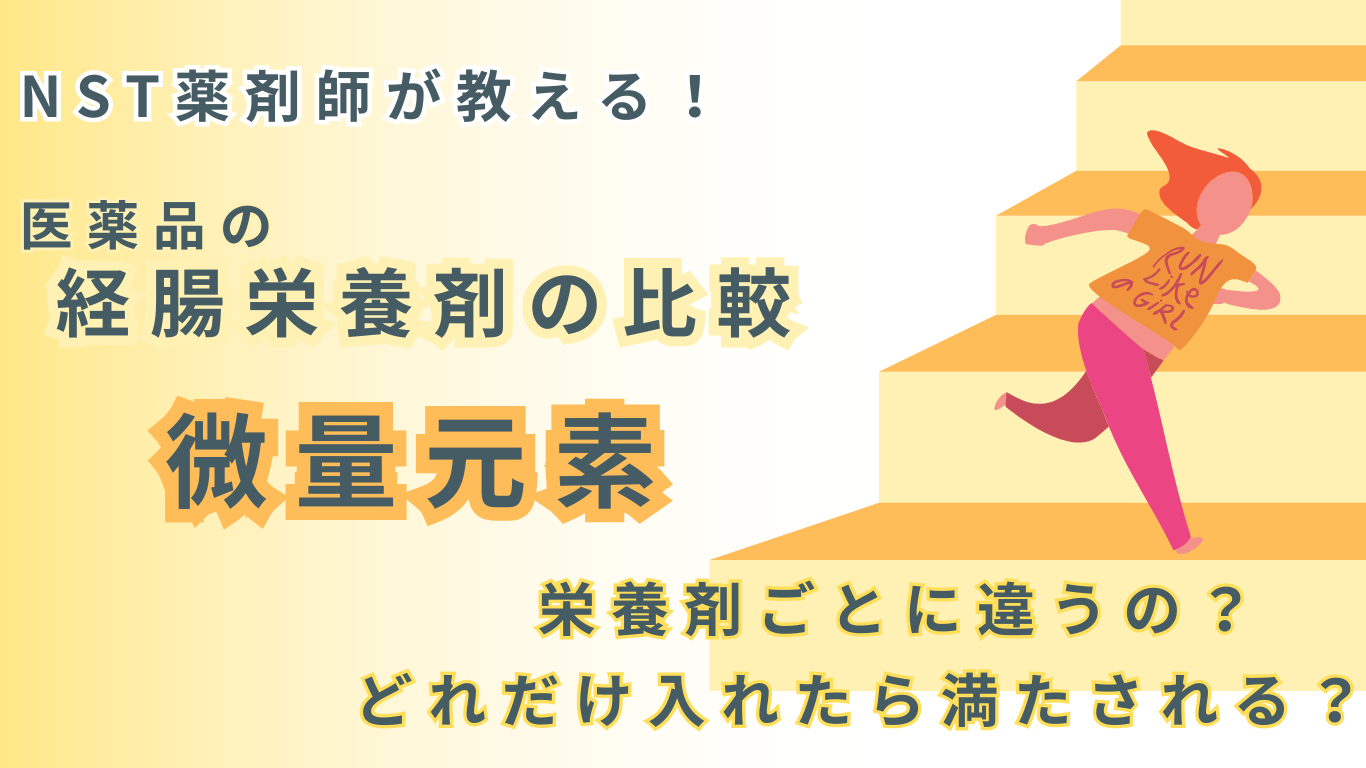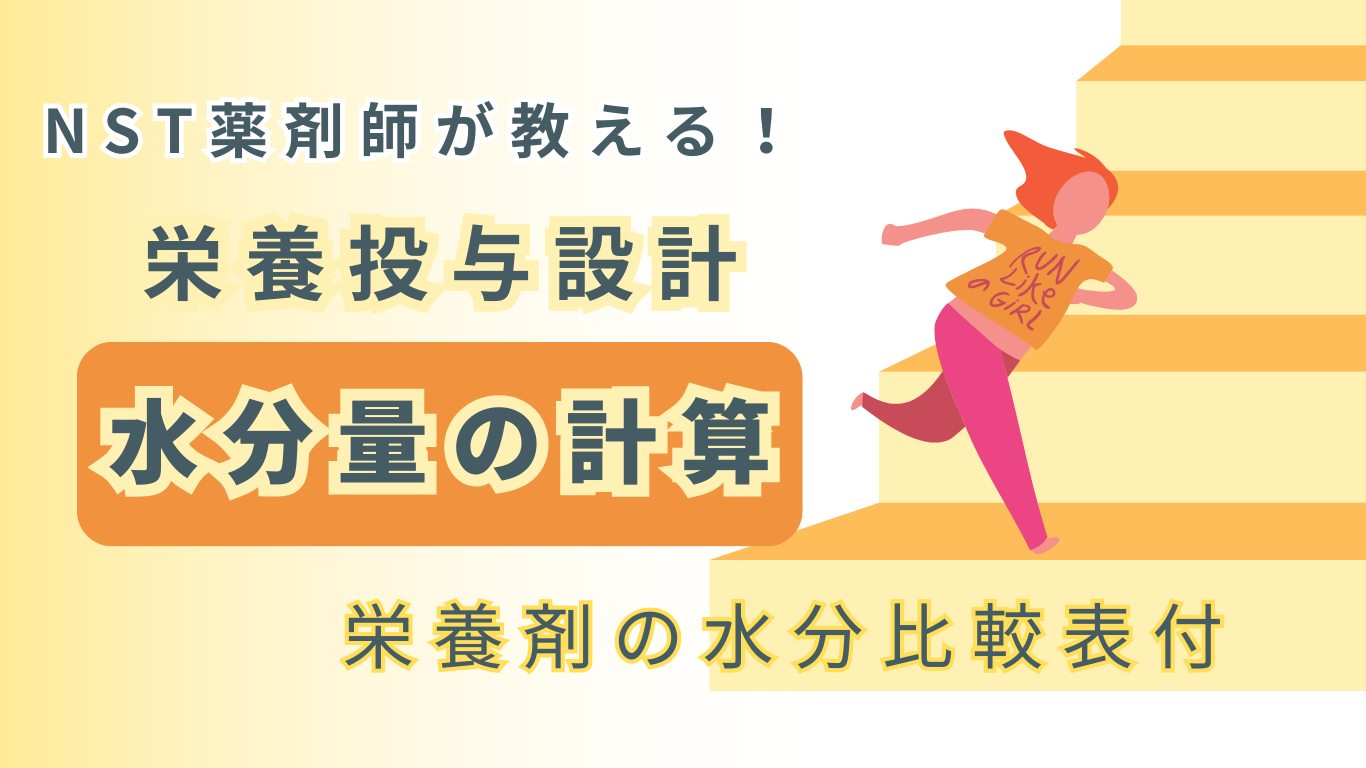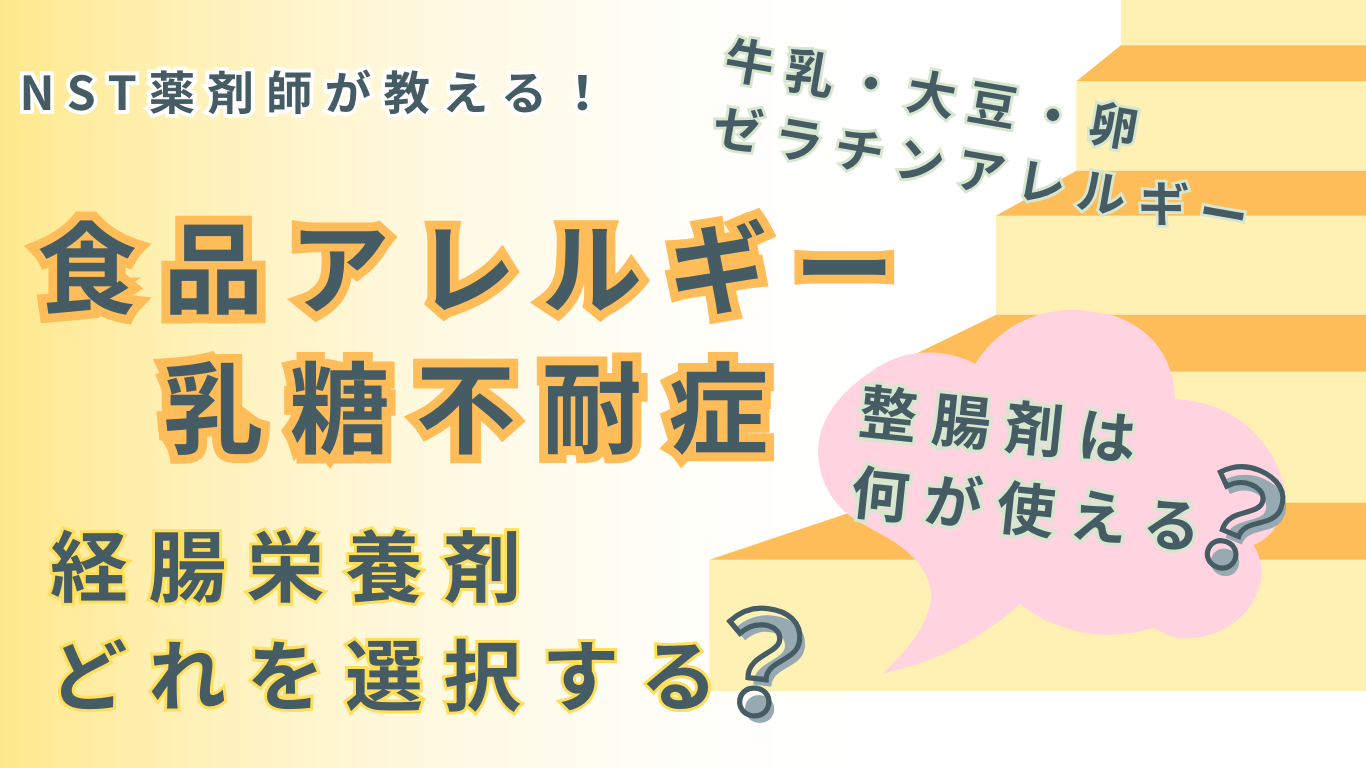経腸栄養剤のおさえるべき特徴5選!NST薬剤師が教える栄養剤の比べ方 食品との比較にも役立つ

NST薬剤師のkeikoです。栄養剤について無知で調べ方も分からなかった薬剤師が、ここをおさえたら栄養剤が理解できた!という5つのポイントをご紹介します。
栄養について興味はあるのに、栄養剤について全くの無知でした。私は病院薬剤師なので、同じ職場に管理栄養士さんがいて比較的聞きやすい環境にいます。ただ、栄養剤って病院薬剤師だけでなく、薬局薬剤師、とくに在宅を担当している方だと患者さんや患者さんご家族へ紹介する場面があるのではないでしょうか。
そもそも薬剤師って薬の調べ方は分かるのに、栄養剤の調べ方って分からない。
なんなら、医薬品の栄養剤についてもそんなに詳しくない!という方も多いと思います。
(だって、栄養剤って他の薬と違って色々な成分が入っているし。添付文書みたってそんなに違いが分からない。他の薬だったら有効成分がだいたい1つだからわかりやすいのに・・・と思う方いませんか?私はそう思いましたし、輸液の比較表みたいに経腸栄養剤の比較表も製薬企業からもらったものがあるけど、あれを見てもちんぷんかんぷん・・・)
このように、何を基準に違いを調べたらいいか分かっていませんでした。
そこで医薬品含め、食品の栄養剤とも比べるときに役立つ
栄養剤のおさえるべき特徴を5つまとめました。
1.成分栄養剤、消化態栄養剤、半消化態栄養剤のどれにあたるのかを覚えよう
経腸栄養剤がどれにあたるのかを知っておくと、いつ、どんなときに使われるのかを理解できます。
他の薬と違って、毎年毎年新しい薬が出てきたりしないので、この薬が成分栄養剤、消化態栄養剤はこれ、といって覚えたら良いと思います。最近追加になってる医薬品の経腸栄養剤は半消化態栄養剤の中の半固形製剤くらいですね。
| 成分栄養剤 | 消化態栄養剤 | 半消化態栄養剤 | |
| 経腸栄養剤名 (医薬品) | エレンタール エレンタールP へパンED | ツインラインNF | エンシュア・リキッド エンシュア・H ラコールNF(液体) イノラス エネーボ アミノレバン ラコールNF半固形 イノソリッド半固形 |
薬だけでなく、栄養剤もこれらに該当するので、職場の採用品がどれに該当するのかを覚えておくと良いですね。
※私が購入した書籍では、以下2つは医薬品だけでなく、市販の栄養剤の一覧表もついているので1個1個調べるのが億劫だ!という方にはおすすめです。本屋さんで自分なりに見やすいものを選び、どちらも(無意識でしたが)佐々木雅也先生の著書でした。①はNST資格試験を受験しようと考えている方、基本的な知識を網羅するのに適しています。②は現場での実際の処方設計や困ったときに使える内容です。
①メディカルスタッフのための栄養療法ハンドブック
②エキスパートが教える輸液・栄養剤 選択の考え方
各々の特性
経腸栄養剤がどれに該当するのかを覚えて、いざ臨床に生かすためには各々の特性を理解することが必要です。
では、その3種類の特性の違いは知っていますか?薬剤師であれば大学で習ってきていたので、成分栄養剤<消化態栄養剤<半消化態栄養剤の順でタンパク質の細かさが違って消化が必要か必要じゃないってことですよね?そんなの知ってます!と思いましたが、実はもう少し違いがあります。
私が(恥ずかしながら)知らなかったのは、成分栄養に脂肪がほとんど入っていないこと。これは結構大事なポイントでした!!成分栄養のエレンタールは脂肪がほとんど入っていないため、クローン病や潰瘍性大腸炎、急性膵炎に使用される。と臨床とつながってきます。
以下、まとめたのでこの違いは知っておきましょう。
| 成分栄養剤 | 消化態栄養剤 | 半消化態栄養剤 | |
| タンパク質 | アミノ酸 | ペプチド | タンパク質 |
| 脂肪 | ほとんど含まれない | 少ない | 多い |
| 消化 | 不要 | 一部不要 | 必要 |
| 味 | 苦い | < | マイルド |
| 形態 | 粉(溶解が必要) | 粉(溶解が必要) 液体 | 粉(溶解が必要) 液体(大半をしめる) |
| 腸管の負担 | 軽い | < | 重い |
2.製品1個あたりのカロリーと濃度を覚えよう
株式会社大塚製薬工場のHPからもダウンロードできる”医薬品経腸栄養剤組成一覧”から栄養剤を比較してみようとする方多いのではないでしょうか?これをみると、”100kcalあたり”で比較されています。他にも”1個あたりや”100mLあたり”で表になっていますが、一体どれで比べるのがわかりやすいのか・・・。数字が沢山並べられていて基準が一つではないところが私のつまづきポイントでした。
色々思考錯誤した結果、私としての結論は
製品1個あたりのカロリーと濃度を覚える
です。薬でいう有効成分の量=栄養剤ではエネルギー量だからです。
【具体例】
エンシュア・リキッド → 1個250mL缶、濃度 1 kcal/mL
エンシュア・H → 1個250mL缶、濃度1.5kcal/mL
薬剤師は、”1個あたり”で比較することが多いです。薬だったら処方箋に個数(gやmLで書かれていることもありますが、患者さんへのお渡しは個数単位だと思います)、食品でも購入は1個単位です。そのため”1個あたり”で考えることが良いとの結論になりました。複数規格があるものは注意が必要ですが、その辺は薬剤師であれば対応しやすいと思います。アムロジピン2.5mgと5mgなど複数規格の対応は日常茶飯事ですからね。
3.濃度と水分量の関係を知る
【結論】
1 kcal/mL の製品 → 約80~85% の水分量
1.5kcal/mL の製品 → 約75%前後 の水分量
え?と思った方いらっしゃいませんか?
実は、1個xmLの製剤=水分量xmLではないんです!!
エンシュア・リキッドは1缶250mLだから、水分も250mLだと思いませんか?
実は違います!!このように投与水分量を決めてしまうと実際の水分量はもっと少なくて脱水になってしまいます。
【具体例】
エンシュア・リキッド(1kcal/mL) → 1缶250mL中、水分は213mL(85%)
エンシュア・H (1.5 kcal/mL) → 1缶250mL中、水分は194mL(78%)
これ、落とし穴だと私は思ってます。Drから質問があったらこのまま答えてしまいそうではないですか?ここで気づくことができてラッキーです。
話を戻しまして上記に示したように、
濃度によってざっくり水分量が決まっているのでこれを覚えましょう。
製剤毎に若干異なるので、いざ投与するために具体的な水分量を計算するときには製品毎の水分(%)から計算できるようになっていれば良いです。
添付文書にも”水分”で記載がありますよ。
ご高齢者で脱水リスクがある方は濃度低め、心不全で飲水制限がある方は濃度高め、など経腸栄養剤を選ぶポイントになりますね。
4.エネルギー比率(タンパク質:脂質:糖質=P:F:C)を知ろう
いざ、エネルギー必要量を計算してタンパク質たくさん入れたいな・・・と思って添付文書みても1個あたりの大きさが違うから比べにくい!100kcalあたりで比べても良いけど、最終的に何個投与したいんだっけ?・・・と私としては複雑になって混乱してしまいます(><)
そこで、製品毎のエネルギー比率(タンパク質:脂質:糖質=P:F:C)をみると、タンパク質が多い製剤、脂質が多い製剤、ほとんど糖質の製剤など比較しやすくなります。
【具体例】
エンシュア・リキッド → P:F:C=14:31:55
エンシュア・H → P:F:C=14:31:55
ラコールNF(液体) → P:F:C=18:20:62
イノラス → P:F:C=16:28:56
エンシュアはリキッドとHでは濃度が違うだけで組成が同じということが分かります。
ラコールよりもエンシュアの方が脂質が入っていることもここから分かりますね。
5.処方設計熱量から、ビタミンや微量元素が充足されているか知ろう
処方設計熱量とは、製品がつくられるときに1日に投与することを想定しているカロリー(熱量)のことです。そのカロリーを1日で投与すると想定してつくっているため、そのカロリー分を投与しないとビタミンや微量元素が充足できないように設計されています。
・・・?はてなマークが浮かんだ方が多いのではないでしょうか?
どういうことかというと、
【結論】
処方設計熱量分のカロリー(=添付文書の用法用量の標準量)を投与しないと
1日に必要なビタミン、微量元素を投与できない。
ということです。
実際には製品によって、ビタミンや微量元素の量や入っているものが異なります。
薬であれば添付文書に有効成分量が書いてあり、ビタミンや微量元素も同様に書いてあります。
しかし
数字がたくさん並んでいて比べにくい!
”mg”、”g”、”μg”など製品毎に単位がバラバラ
ましては、よく知らない記号が書いてあるものも・・・”RE”って何?!
と、お手上げ状態・・・
それに全部のビタミンや微量元素で必要な量とか覚えてないし、とりあえず投与してたらビタミンも微量元素も入ってるし問題ないよね?
・・・という間違った認識から、まずは
処方設計熱量分を投与していないと、ビタミンや微量元素の欠乏が起こりやすい
ということが理解できたら良いと思っています。
【具体例】
エンシュア・リキッド → 1870kcal(1500~2250kcal)
エンシュア・H → 1870kcal(1500~2250kcal)
ラコールNF(液体) → 1600kcal(1200~2000kcal)
イノラス → 1200kcal( 900 ~1500kcal)
※()内は添付文書上の標準投与量
このように、エンシュアやラコールよりもイノラスの方が少ないカロリー投与で必要なビタミンや微量元素を補うことができます。
(添付文書上の標準量には幅がありますが、だいたい中間くらいを考えたらOKです。)
高齢化に伴い、維持エネルギーが少ない方や摂取負担のために少ない投与しかできない方が多く、新しい製剤は処方設計熱量が少ない傾向にあります。
以上、栄養剤を調べるときにおさえるべき特徴5選でした。
途方もなく一つ一つ比べていた方や考え方や調べ方が分からなかった方の役に立てたら嬉しいです。