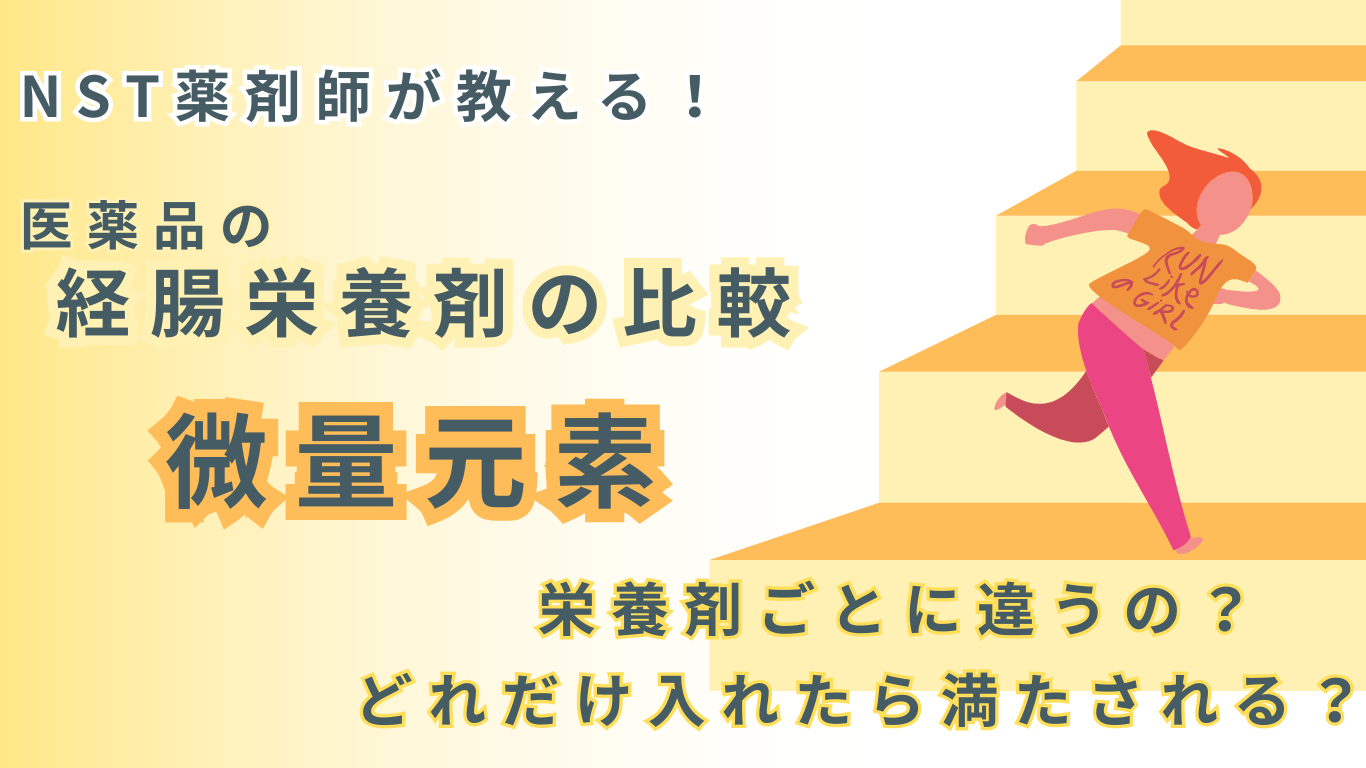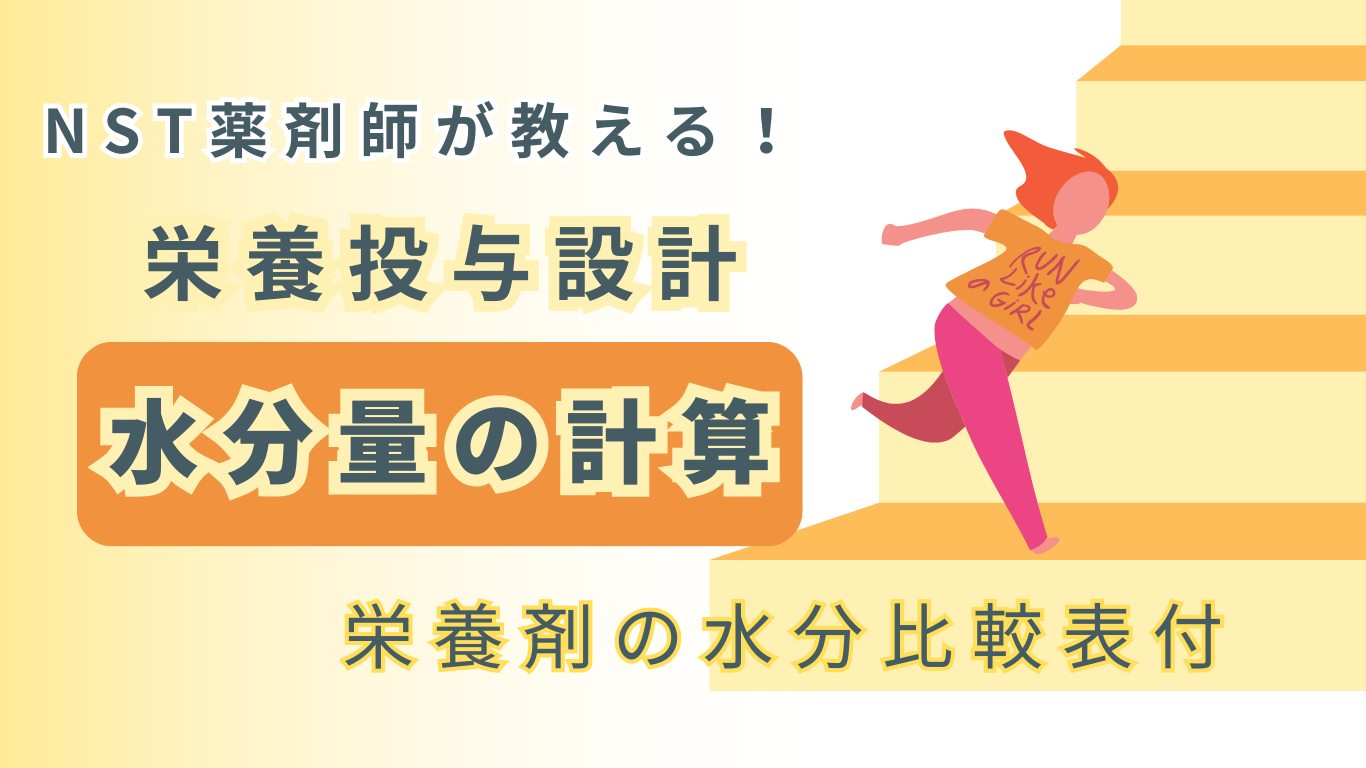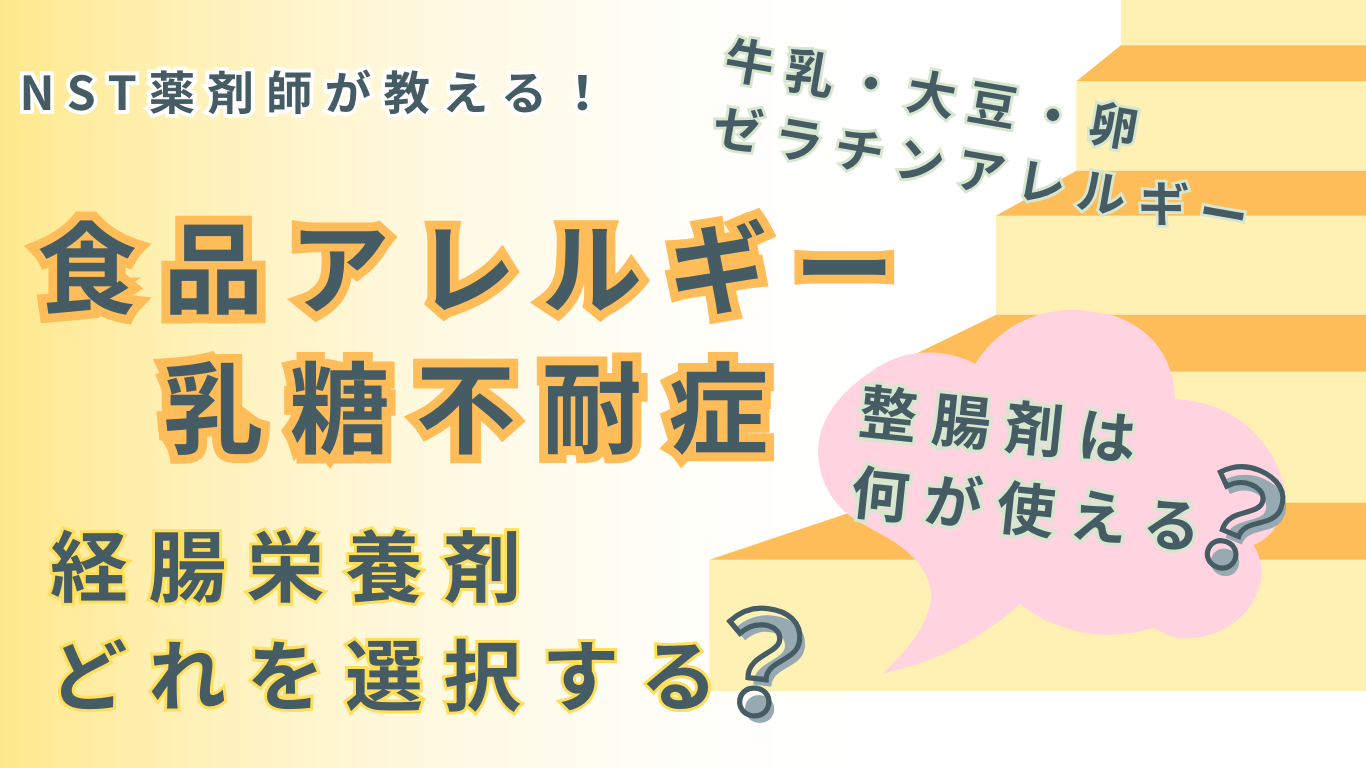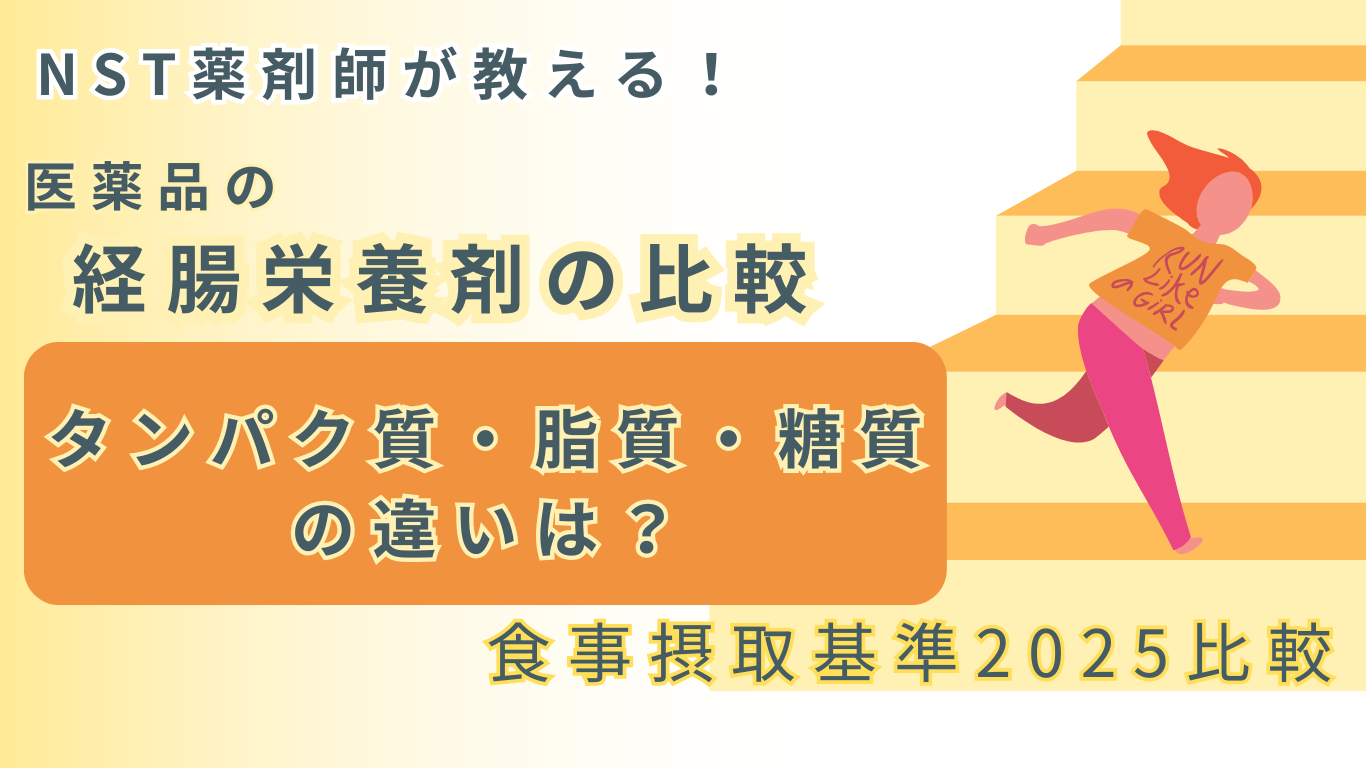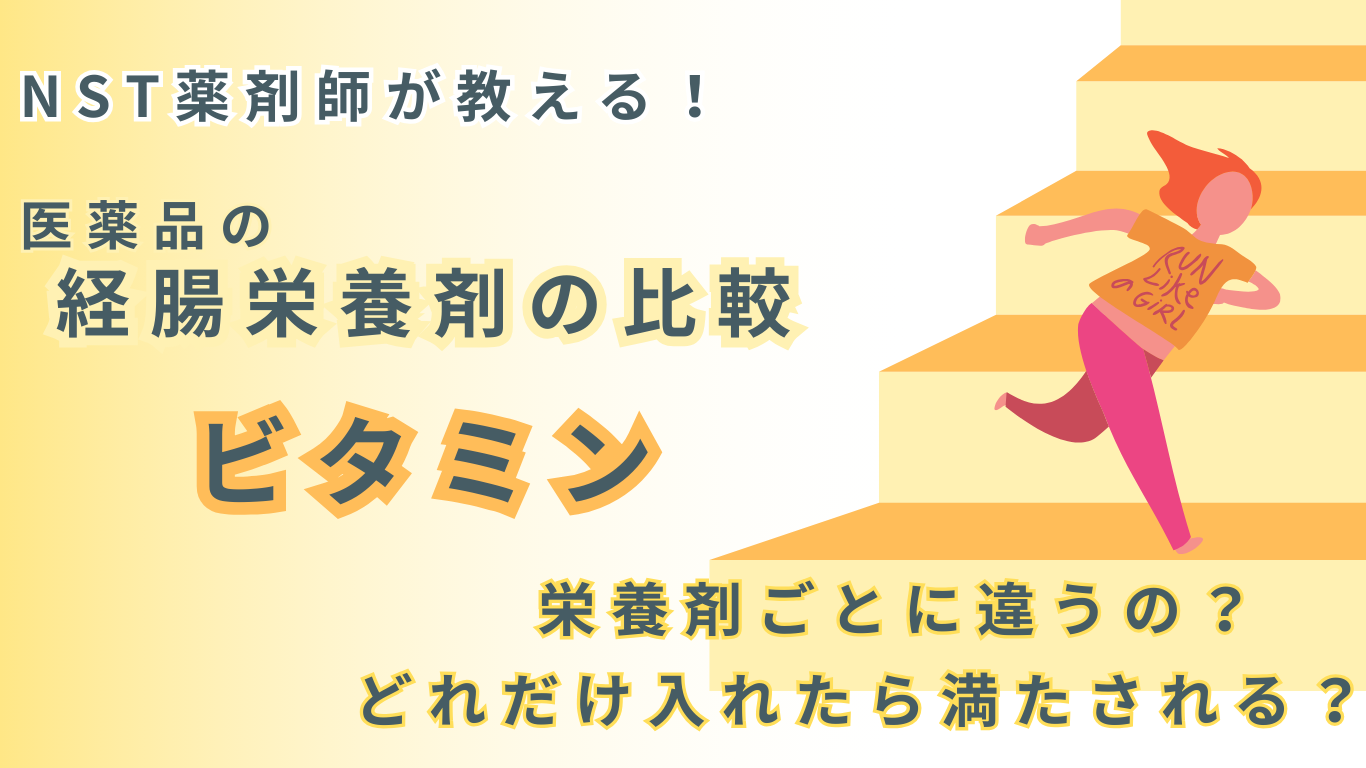【NST薬剤師解説】経腸栄養における薬の投与方法と注意が必要な薬(よくある疑問付)
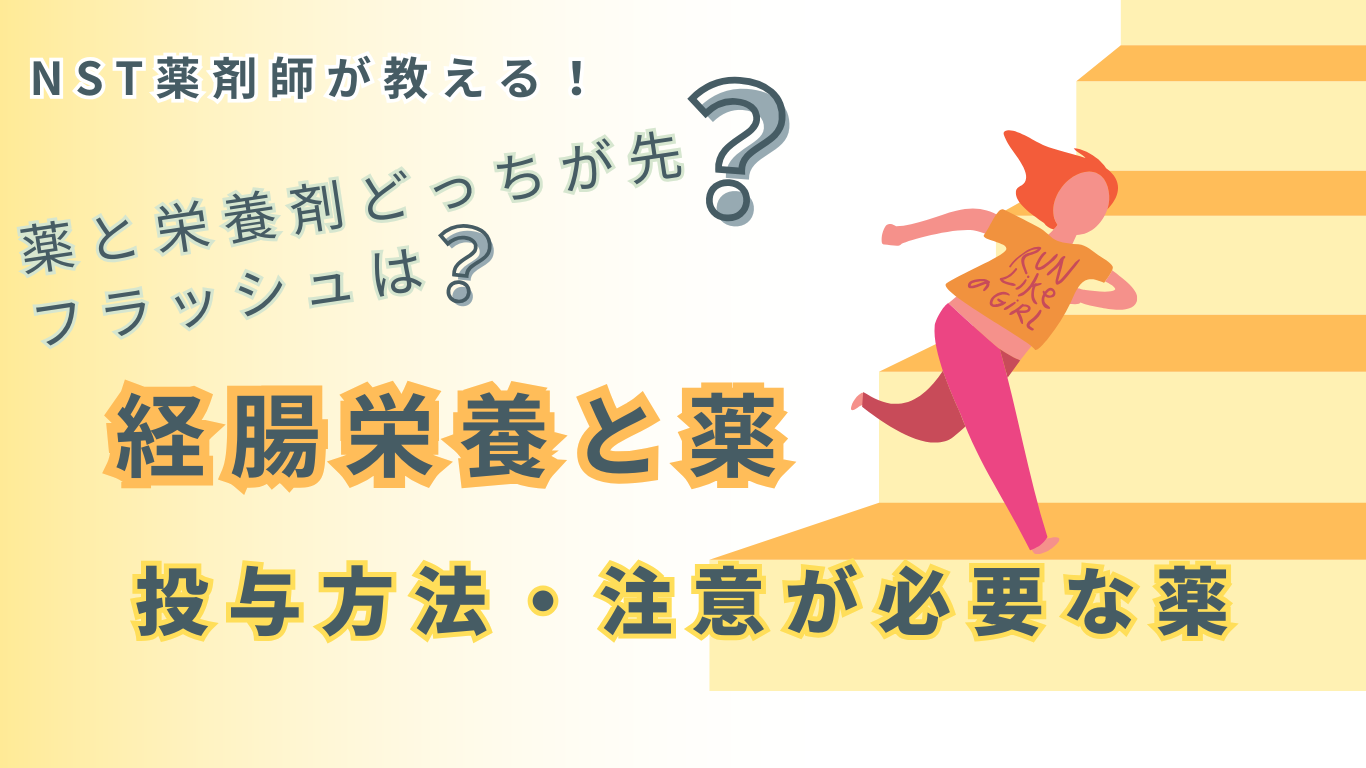
いざ患者さんやご家族に聞かれると、「薬や栄養剤を実際どのように投与しているのか」「何に気を付けたらいいのか」が説明できない…。
経腸栄養は「実際にどう投与されるのか」がイメージしづらい分野だと思います。
私は一人の薬剤師として、これまで経腸栄養の患者さんやご家族に栄養剤をお渡ししてきました。
その中で感じたのは、薬と栄養剤の関係を理解しないまま投与すると、思わぬトラブルが起こるということです。
たとえば、薬が原因でチューブが詰まってしまったり、薬や栄養剤の効果が十分に発揮されなかったり──。
実際、カテーテル閉塞の原因の多くは薬によるものとも言われています。
この記事では、薬と経腸栄養剤を安全に投与するために押さえておくべき基本を、
「投与方法」「薬剤ごとの注意点」に分けて解説します。
「なぜその順番なのか」「どんな薬に注意が必要か」——その他のよくある疑問も一緒に確認していきましょう。
薬と栄養剤の投与方法
経腸栄養と薬を併用するときに最も大切なのが「順番」と「フラッシュ」です。
この2つを守ることで、チューブ閉塞を防ぐことができます。
投与順番の基本:薬→栄養剤(投与前後でフラッシュ)
つまり、
フラッシュ → 薬 → フラッシュ → 栄養剤 →フラッシュ
の順番を守ることが基本です。
この順番を守ることで、
- 薬と栄養剤が混ざって沈殿・変性を起こす
- 薬の投与を忘れる
といったリスクを大きく減らすことができます。
経管投与のよくある疑問
「食後薬」は栄養剤のあとに投与した方がよいの?
『食後』処方でも、食事影響がない薬なら薬→栄養剤でOKです。
実はコンプライアンス維持の目的で「食後」で処方されている薬が多いです。
一方、吸収が食事に左右される薬については、後述の「食事の影響がある薬」で詳しく解説します。
フラッシュは「白湯」以外でもよい?
経管投与のフラッシュは「白湯」を使うのが望ましいです。
水や生理食塩水は、このような理由で避けた方がよいです。
- 水:冷水では腸を刺激し、下痢のおそれあり
- 生理食塩水:栄養剤と反応し、塩析のリスクあり
点滴では「生理食塩液」でフラッシュが日常ですが、経管投与においては栄養剤と反応し、閉塞リスクになりうるので覚えておきたいところです。
水分はいつ投与する?
薬と栄養剤の投与だけでは水分量が少なく、水分を追加で投与する必要がある患者さんがいます。
おすすめは➊先に必要な水分を投与です。
それには理由があって
・逆流が少なくなる
・誤嚥したときに、栄養剤より安全
だからです。
経腸栄養剤時の必要な水分量についてはこちらの記事をご参考ください
【NST薬剤師解説】栄養投与設計~水分量の計算~(経腸栄養剤の水分比較表付)
栄養剤を持続投与中のとき、薬はいつ投与したらいい?
持続投与中の患者さんでは一時的に栄養剤を止め
薬の投与前後に十分な量の白湯でフラッシュを行えば問題ありません。
なお、薬が食事に影響を受けるタイプであれば、栄養剤を止めてから薬を投与するまでの時間を調節する必要があります。
薬はどうやって投与する?
- 従来の方法:粉をそのまま溶かして投与 → 完全に溶けずカテーテル閉塞の原因になりやすい
- 簡易懸濁法:「内服薬 経管投与ハンドブック」で投与可能か確認できる
“粉”といっても「細粒」「顆粒」「錠剤を粉砕」「脱カプセル」など様々な形態があり、
すべてが水に完全に溶けるわけではない点に注意が必要です。
具体的な方法やメリット、簡易懸濁法ができるかどうか調べる方法等についてはこちらの記事をご参考ください。
粉砕・一包化・簡易懸濁の目的、必要な知識と調べ方
薬剤ごとの注意点
キレート形成する薬
経腸栄養剤にはカルシウム(Ca)やマグネシウム(Mg)などが多く含まれています。
そのため、栄養剤中の金属イオンと結合しやすい薬は吸収が低下します。
※おまけ:栄養剤の投与「前」の理由
薬の投与は、体内に十分吸収させたいものを最初に投与するのが原則だからです。
たとえ2時間後に薬全てが吸収されていなくても、影響する薬を最小限にできると考えられます。
一方、栄養剤を先に投与すると、2時間後に栄養剤がお腹に残っていたら薬の吸収が妨げられてしまいます。
ただ、これは考え方であって、臨床では患者さんの状態や投与の煩雑さを考慮して薬が後になる場合もあるので、そこは患者さんをみて選択ですね。
キレート形成する薬の例
- ニューキノロン系(抗菌薬)
- テトラサイクリン系(抗菌薬)
- ビスホスホネート系(骨粗鬆症薬)
- レボトパ(抗パーキンソン治療薬)
この辺りがよく使われる薬ではないでしょうか。
他にも以下のような薬はキレート形成すると添付文書に書いてあります。
(ご参考まで)
- イソニアジド(抗結核薬)
- セフジニル(抗菌薬)
- エルビテグラビル、ビクテグラビル,ラルテグラビル(抗HIV薬)
- エンタカポン、オピカポン(COMT阻害薬、抗パーキンソン治療薬)
- ドロキシドパ、レボドパ(抗パーキンソン病薬)
- バダデュスタット(HIF-PH阻害剤、腎性貧血治療薬)
制酸薬(胃薬)と粘度可変型栄養剤
粘度可変型栄養剤は、体内で粘度が変わる製品です。
多くは胃酸(pH低下)によって粘度が増し、半固形化します。
液体で投与できるため、手技は簡単です。
ただし、PPI(プロトンポンプ阻害薬)やH₂ブロッカーなど胃酸を抑える薬を併用すると、
想定より粘度が上がらず、胃内滞留や逆流のリスクが増すことがあります。
このような場合には検討すること:
- 制酸剤の中止
- 粘度に影響されないタイプの栄養剤へ変更
※「投与タイミングをずらす」と医師より指示がある場合がありますが、制酸薬を定時内服している際は、定常状態のため効果がないと考えられます。
粘度可変型栄養剤の例
- マーメッドワン
- マーメッドプラス
- ハイネイーゲル
- BeSolid(ビーソリッド)
- わのか(和の奏)
食事の影響がある薬
食事の影響がある薬は、栄養剤の投与によっても吸収が左右されることがあります。
- 「空腹時」「食前」の薬
薬を投与後に栄養剤を投与するまで時間をあける必要があります。 - 「食後」の薬
栄養剤投与後に、薬を投与する必要があります。
栄養剤の方が投与時間が長いことが多いので、薬の投与を忘れないように注意が必要です。
前述したように、コンプライアンス維持目的であることも多いため食事に影響がある薬かどうかは確認しましょう。
食事の影響がある薬の例
空腹時・食前推奨
- イトラコナゾール(イトリゾール®)
- セマグルチド(リベルサス®)
- エンテカビル(バラクルード®)
- アナモレリン(エドルミズ®)
- ビラスチン(ビラノア®)
食後推奨
- ブロナンセリン(ロナセン®)
- アトバコン(サムチレール®)
- レゴラフェニブ(スチバーガ®)
※おまけ 食直前の糖尿病薬
- αグルコシダーゼ阻害薬(ボグリボースなど)
- 速効型インスリン分泌促進薬(ミチグリニドなど)
経腸栄養のみの患者さんでは処方例は少ないですが、栄養剤投与速度が遅い場合は薬の効果と血糖上昇に時差が生じ、低血糖のリスクがあるため注意が必要です。
まとめ
- 薬と栄養剤の投与方法
- 投与順番:薬→栄養剤 投与前後はフラッシュ
- 投与順番:薬→栄養剤 投与前後はフラッシュ
- 経管投与のよくある疑問
- 「食後薬」でも食事の影響がない薬だったら薬→栄養剤の順番で投与
- フラッシュは「白湯」が望ましい(水や生食×)
- 必要な水分は薬や栄養剤の前に投与orフラッシュの量を増やす
- 栄養剤の持続投与中は、一旦栄養剤を止めて薬を投与する
- ★投与前後のフラッシュはしっかりと
- 薬は簡易懸濁法で投与する
- 薬剤ごとの注意点
- キレート形成する薬は栄養剤投与前に投与間隔をあける
- 制酸薬と粘度可変型栄養剤は併用しない
- 食事の影響がある薬は投与間隔をあける
経腸栄養は、薬剤師にとって「実際にどう投与されるのか」がイメージしづらい分野です。
今回解説させていただいた、薬・栄養剤の経管投与について正しく理解し、
薬が原因のトラブルを未然に防ぎ、患者さんに安全に薬を届けていきましょう。